2003.05.31〜06.01更新
つばくらめ【燕】つばめ。つばくろ。玄鳥。乙鳥(イツチョウ)。
大槻文彦編『大言海』つばくら【燕】つばくらめ(燕)の略。字類抄「芻、ツバクラメ」『鮮嚢鈔』、一、五十八條「芻、ツバクラ」竹取物語「中納言くらつ麿にの給はく、つばくらは、いかなる時にかねを産むと知りて、人をばあぐべきとの給ふ」呼子鳥、上「つばめ、つばくらなり」飼鳥必用、上「つばくら、此鳥三月前後、江戸にて子を生立候て、秋の節、何國へか飛かへるなり」〔3-418-2〕
つばめは、遙かな常世の國から、祖先同様に渡り来る鳥ゆえ、長寿と冨貴と恋愛とをもたらす、春の神の使者する。《『日本民俗語大辭典』840頁より》
明治の文豪である夏目漱石『野分』の一に、「鴻雁(こうがん)の北に去りて乙鳥(いっちょう)の南に来(きた)るさえ、鳥の身になっては相当の弁解があるはずじゃ。」とし、『草枕』の十三に、「舟はようやく町らしいなかへ這入(はい)る。腰障子に御肴(おんさかな)と書いた居酒屋が見える。古風(こふう)な縄暖簾(なわのれん)が見える。材木の置場が見える。人力車の音さえ時々聞える。乙鳥(つばくろ)がちちと腹を返して飛ぶ。家鴨(あひる)ががあがあ鳴く。一行は舟を捨てて停車場(ステーション)に向う。」、明治33年の英国留学渡航日記に「9月12日(水) 夢覚メテ既ニ故郷ノ山ヲ見ズ 四顧渺茫タリ 乙鳥一羽波上ヲ飛ブヲ見ル 船頗ル動揺 食卓ニワクヲ着ケテ顛墜を防グ」とあって、「乙鳥」の語がそれぞれ見える。が、この読みを音で「イッチョウ」訓じて「つばくろ」と読むのだと知り、この鳥があの「つばめ」のことだと知っている人はどのくらいるだろうか?漱石は俳句を嗜み、
乙鳥(つばくろ)や 赤い暖簾の 松坂屋 《『漱石俳句集』新潮文庫》
といった句も詠んでいる。この語を発句に詠んだものとしては、江戸時代の小林一茶の句に、
いつの間に乙鳥は皆巣立けり 西国紀行 寛7《HP『一茶発句全集』による》
とし、与謝蕪村の遺稿集にも、
花に啼聲としもなき乙鳥哉
と詠まれているが、
これらの作品群などに見える漢字表記した動・植物名を現代の人がどれほど読みこなすことができるのか、古典読解力を再度問う大事な時期を迎えている。なぜならば、その読解力をも失いつつあるのが昨今の国語事情なのだから……。実際、「つばめ」を季題にした俳句や短歌は、すべて「燕」の表記字をもってしか記載しなくなってしまっている。漱石自身、上記に記載した『草枕』のなかでも、
身を斜(はす)にしてその下をくぐり抜ける燕(つばめ)の姿が、ひらりと、鏡の裡(うち)に落ちて行く。
燕(つばくろ)は年々帰って来て、泥(どろ)を啣(ふく)んだ嘴(くちばし)を、いそがしげに働かしているか知らん。燕と酒 の香(か)とはどうしても想像から切り離せない。
と「燕」の表記で「つばめ」「つばくろ」と用いてもいる。
「乙鳥」を合成字で「鳥」+「乙」と表記した「弄」の用例が下記に示した古辞書である観智院本『類聚名義抄』に見えている。こちらが原字で、分解字としたのが「乙鳥」なのか?その疑問を解決するために少しく検証して見る必要がある。手始めに1、『漢語辞典』と『国語辞典』を手がかりに調べていく。そして、2、漱石自身がこの鳥をどう表記してきたのかについてもDBを駆使して調べていく。すると、漱石は上記のうち「玄鳥」の語を用いていないことを認知するのである。現代の私たちより漢詩文素養の高い世代にあっても、その選択は、未知と既知という概念を有しているのであろう。そして、逆に3、「玄鳥」の用字を用いている明治時代の資料も検討していくのである。この1・2・3の検証作業で得られたデータを整理してみると、この「報告書」は完成することになる。
【和 名】 ツバメ
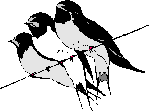 【学 名】 Hirundo rustica
【学 名】 Hirundo rustica
【英 名】 Barn Swallow
 【漢字名】 燕
【漢字名】 燕
【科目名】 スズメ目ツバメ科
【異和名】 ツバクロ・ツバクラ・ツバクラメ・マンタラゲシ
【異英名】 House Swallow/Swallow
【異漢名】 乙鳥・玄鳥
【S/M 学】 Hirundo
古辞書資料
『倭名類聚抄』「芻(ツハクラメ) 剔故以名之」「燕鳥 尓雅集註云―鳥見反豆波久良米自胎小烏也」《国立歴史博物館藏、卷第七5ウ一・二》
『新撰字鏡』「缸 居久反上鶏豆波比良古」「瑾璋采利反豆波比良古」「弄 同於乙入畢豆波比良古」「芻」延見反言弄六字同」《卷八483二》
観智院本『類聚名義抄』「ツハクラメ(燕)僧上ノ四八○(芻)僧上ノ四八○(玄鳥)僧中ノ一一〇○(弄)僧中ノ一一六○(燕鳥)僧中ノ一三〇○(畢)僧中ノ一三〇」(正宗敦夫編『類聚名義抄假名索引』参照)
「燕 音宴 ヤスムス(シ) ツバクラメ ツヽム/又音烟國名」《僧上48三》
「芻 ツバクラメ/与上通用」《僧上48四》
「玄鳥 ツバクラメ」《僧中110八》
「弄 乙二正/英物反/ツバクラメ ツヽ」《僧中116六》
「燕鳥 烏見反/ツバクラメ」《僧中130五》
「畢 同」《僧中130五》
黒川本『色葉字類抄』に、「芻(ヱン/ツハメ)ツハクロメ/軻泥(カムテイ)玄乙同」《動物・中21オ七》
白河本『字鏡集』「芻(エン)燕同/ツハクラメ 正/畢同」《九卷、動物部・鳥部365二》
『温故知新書』「燕(ツハメ) 芻(同)」《氣形門六》
『伊京集』「燕(ツバメ) 芻又乙同」《畜類》
広本『節用集』「燕(ツバメ/ヱン)[平・去]―与芻同字。又燕ハ國(クニ)ノ之名(ナ)ノ時平聲也。月令曰。玄鳥ハ春到秋水帰ル。詩ノ註ニ燕ハ乙鳥ナリ。有二三種一。紫胸軽小ナル者ハ越燕ナリ。色白者数百歳ノ燕ナリ。胸ネ斑聲_大ナル者胡燕ナリ也。異名、風乙。玄乙。差池。芥觜。王謝。烏夜公子。玄乙鳥。天女。■■■玄夜。土撥滅(ツバメ)合紀。〔氣形門413六〕
『異名分類抄』「燕 つはひ つはひは古訓なり、天智紀に云、六年葛野ノ郡献白燕(つばひ) 私記津波比」
『物類称呼』二7「燕、つばめ、但馬國にてひいごと呼び、和名に爾雅集記を引きて、つばくらめと註せり、今俗につばめといひ、又つばくらと云ふは、後人其の語をはぶきて呼ぶ也、片田舎の人はつばとばかりも呼び、又歌にはつばくらめとも、つばめとも詠ず、つばくらとは詠格なし、俳諧にはつばくら共作例有り、又つばくらめとは、土くらひの和訓也と、篤信翁の説也、又胡燕、越燕、漢燕等有り、胡燕はやまつばめと云ふ、越燕よりは、稍(やゝ)大にして山上岩穴(がんけつ)にすむ、巣は横に長く、脇の方より出入す、越燕は巣の上より出入す、但馬國村岡にて、妙見ひいごと云ふは胡燕なるべし」〔生活の古典双書17・56頁〕
夏目漱石『明暗』に、「突如として彼女が関と結婚したのは、身を翻(ひる)がえす燕(つばめ)のように早かったかも知れないが、それはそれ、これはこれであった。」


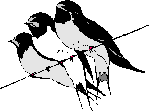 【学 名】 Hirundo rustica
【学 名】 Hirundo rustica
 【漢字名】 燕
【漢字名】 燕