
国語史の課題
810135
坂下ちひろ枕草子
(まくらのそうし)【成立】一〇〇〇年(長保二年)ごろ【製本数量】一冊。三二一〜三二三の章段から成る冊子。現在では三巻本がもっとも親しまれている。【著者】清少納言【識字】本云徃事所持之荒本紛失年久更借出一両之本令書留之依無 證本不散不審但管見之所及勘合舊記等注付時代年月等 是亦謬案歟 安貞二年三月耄及愚翁在判 古哥本文等雖尋勘時代久隔和哥等多以不尋得纔見事 等在別紙 校合再移失點了 秀隆兵衛督大徳書之 文明乙未之仲夏廣橋亜槐送實相院 准后本下之本末兩冊見示日余書冩所 希也嚴命弗獲點馳禿亳彼舊本不 及切句此新舊讀而欲容易故比校之次 加朱點畢 正二位行権大納言藤原朝臣教秀(陽明文庫本)【諸本・所蔵】三巻本…陽明文庫蔵本、宮内庁書陵部蔵本、陽明文庫蔵乙本、吉田幸一氏蔵富岡家旧蔵本、高松宮家蔵本、田中重太郎氏蔵弥富破摩雄氏旧蔵本、吉田幸一氏蔵伊達家旧蔵本、前田家本、大東急記念文庫蔵古樺堂文庫旧蔵本、内閣文庫蔵本 能因本系統本…学習院大学蔵三条西家旧蔵本、野坂元定氏蔵本、吉田幸一氏蔵富岡家旧蔵本、河野信一記念文化館蔵高野辰之氏旧蔵本 前田家本…前田旧侯爵家尊経閣蔵本 堺本系統本…高野辰之氏旧蔵本、吉田幸一氏蔵高野辰之氏旧蔵本、旧台北大学旧蔵本、岸上慎二氏蔵山井我足軒本、田中重太郎氏蔵朽木文庫旧蔵本、群書類従所収本、京都大学蔵本、宮内庁書陵部蔵本。(参考資料) 「現在伝わる『枕草子』の諸伝本は三巻本、能因本、前田家本、堺本の四系統に分類されている。この四系統の伝本は、その組織、本文ともにそれぞれかなり異なった様相を呈していて、本文に関してだけ言っても、この作品は相当程度以上に複雑な事情の下にあるといっていい。」( 石田穣二、1979)この四系統のどれが最も原本に近いかは諸説に分かれているようだ。本論文の主旨とはずれるため、この諸本についての説明は割愛する。【翻字】田中重太郎『枕冊子全注釈』、吉沢義則『校注枕草子』(上下二冊)【国語資料】A、文体…仮名ぶみの散文表現。仮名を主体とし、漢字を用いる場面でもその表音性から離れることがない。類聚章段・随筆章段・日記回想章段の形態を持つ。B、語彙…強調語の多用。「いと(ヒドク)」七一五語、「いみじく(ヒドク)」三〇三語、「いたく(ハナハダシク)」四一語。価値評価の順位が「よし(高貴ダ、ヨイ)」「よろし(普通ダ、悪クナイ)」「わろし(貧シイ、ヨクナイ)」「あし(悪イ)」であるのに対し、その使用頻度も一六八語、二一語、四七語、三八語となっている。C、音韻D、字音E、仮名遣い…漢字で書いたものを訓読みさせることはない。仮名表記の困難なものに限って漢字を用いる。諸本によって、仮名遣いや清濁、それらの表記も違う。三巻本…をまへ、能因本…御前、前田本…御前(第三段「正月一日は」)、堺本…「?」。【影響】梁塵秘抄「物尽しの歌」(類聚章段の影響)、無名草子「女性論」、徒然草(随筆文学)【公開状況】β版 古典文学講座 『 枕 草 子 』 の 世 界■解説・本文校訂・補注■浜 口 俊 裕
平家物語
(へいけものがたり)【成立】一一八三(寿永二)〜一一六九(建久七)年ごろ?(後鳥羽院時代)【製本数量】一方流系統…覚一本から流布本に及ぶ系列で、十二巻の後に「灌頂の巻」を加えた十三巻本。八坂流…灌頂の巻を加えない形態。十二巻は全百二十句で成り立っている。【著者】未詳(中山行長?)【識語】龍谷大学附属図書館
【諸本・所蔵】詠むために増補された「読み本」…源平闘諍録・内閣文庫蔵、四部合戦状本・慶應義塾大学その他に蔵、南都本・彰考館蔵、南都異本・彰考館蔵、長門本・赤間神社蔵その他静嘉堂文庫その他に蔵。平曲の語りに用いる「語り本」…屋代本・國學院大学蔵、平松家本・京都大学蔵、竹柏園本・天理大学蔵、鎌倉本・彰考館蔵、覚一本・龍谷大学図書館蔵・高良神社蔵・寂光院蔵・高野辰之氏旧蔵・龍門文庫蔵【翻字】岩波古典大系(上下二冊)【国語資料】
A、文体…和漢混淆文。諸本によって文体や漢語の使い方が多少異なるが、仮名の用いられている分量が比較的多く、振り仮名や捨仮名も数多くの類が見受けられ、漢文式の体裁のものが消化しきれないで混じって祖先の形態を伝えている。「就中に」「被申ければ」「如件」など。漢字では、今日では通用しない二つ以上の文字がしきりに流用されている。「先」と「前」、「学」と「覚」の混用、「誘(イザ)」「境節(オリフシ)」などの宛字。編年体様式と紀伝体様式で綴られた軍記物語。B、語彙…貴族語彙・武家語彙・仏教語彙の多用。漢語が著しく目立つ。「義家(ギカ)」「雅頼(ガライ)」「俊成(シュンゼイ)」といった和製漢語や、「いはんや」「なかんづくに」「詮ずるところ」など漢文訓読の結果発生した語彙も含まれる。擬声語・擬態語、俗語や方言といった日常・卑近的な口頭語であるやまとことばも特徴的。C、音韻…底本には濁点はほとんどない。諸本高良神社本は前代の清濁を明らかに伝えている。E、かな遣い…歴史的仮名遣いが守られている。「ジ」と「ヂ」、「ズ」と「ヅ」の四つ仮名の区別などには乱れがないが、語中語尾の「ヒヘホ」は他の語に紛れて使われている。「和歌の前」→「わかのまひ(舞)」など。【影響】看聞御記、西海余滴集、申楽談儀聞書(平曲家たちの語りの記録)、盲目の法師
琵琶法師によって平曲として語られる。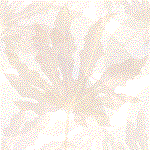 【内容】平氏がわずかの間に中央政界に踊り出て栄華を極めるが、やがてあわただしく滅び去ることを叙した物語。なまなましい現実の戦を描いた修羅闘諍の物語でありながらも、現実逃避の遁世をまじえ、未来の幸福を約束する極楽往生をもって結ばれていることから、隠遁者 や宗教関係者が深く参与したであろうことが想像される。(200101.26記)
【内容】平氏がわずかの間に中央政界に踊り出て栄華を極めるが、やがてあわただしく滅び去ることを叙した物語。なまなましい現実の戦を描いた修羅闘諍の物語でありながらも、現実逃避の遁世をまじえ、未来の幸福を約束する極楽往生をもって結ばれていることから、隠遁者 や宗教関係者が深く参与したであろうことが想像される。(200101.26記)
