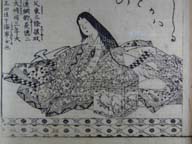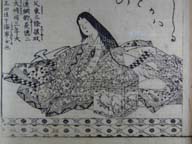
国語史の課題
2001.1.30
810057
山田麻由子とはずがたり
【西暦】1306年 【和暦】徳治1年【作者】後深草院二条【所蔵・写本】伝本は宮内庁所陵部蔵にある江戸初期の写本のみ。【冊数】五巻五冊からなり、前三巻を宮廷編または愛欲編と言い、後二巻を紀行編または修行編とも言う。水色地の表紙に古短冊切を貼って、「とはすかたり」の題名と各巻の番号とを記す。内題も同様に記す。【種類】本文は縦約二八センチ、横約二○・四センチの楮紙(ちょし)を袋綴にしたものに、一ぺ−ジ十一行に書く。和歌は一字乃至三字下げで一行に記す。女流日記文学【翻刻・翻字】『問はず語り』(岩波書店)、新潮日本古典集成『とはずがたり』(新潮社)、対訳日本古典新書『とはずがたり』(創英社)、完訳日本の古典『とはずがたり』(一)(二)【研究書】松本寧至著『とはずがたりの研究』(桜楓社)、玉井幸助著『問はず語り研究大成』(明治書院)【影響】
『増鏡』「あすか川」・「草枕」・「老の波」・「さしぐし」〔A文体〕漢字仮名混じり文〔C音韻〕濁音有り。「おぼゆ」「つぶす」「へだたり」「さらば」【公開状況】―中世の最も知的で魅力的な悪女について―、【原文】蜻蛉日記
(かげろふにっき)【西暦】974年 【和暦】天延2年【作者】藤原道綱母【冊数】序文・上・中・下の四冊【種類】女流日記文学【所蔵・写本】代表的なものには、宮内庁書陵部蔵があり、ほとんどの活字体はこの写本を基にしている。【影印】村上悦子編の桂宮本『蜻蛉日記』(笠間書院・一九八二)、山田清市編『蜻蛉日記』(白帝社・一九六九)(阿波国文庫旧蔵本)、秋山虔編『かげろふ日記』(日本古典文学刊行会・一九七八)【成立】10世紀後半。日本初の女性による日記
【本文】(口語訳)【翻字】大西善明『蜻蛉日記新注釈』(明治書院)、柿本奨『蜻蛉日記全注釈』上下(角川書店)、村井順『かげろふ日記全評解』上下(有精堂)、木村正中・伊牟田経久『日本古典文学全集』の『蜻蛉日記』(小学館)、同氏『完訳日本の古典』の『蜻蛉日記』(小学館)増田繁夫『対訳日本古典新書』の『かげろふ日記』(創英社)、犬養廉『新潮日本古典集成』の『蜻蛉日記』(新潮社)【影響】紫式部『源氏物語』「六条御息所」
〔A文体〕仮名散文〔E仮名遣い〕「ものし」(サ変)が200余り使われ、動作を婉曲に表現している。また「も」を「ん」と読む古い字体が使われている。【公開状況】