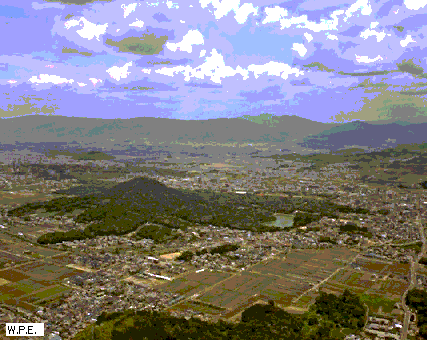
2001.05.07入力~2005.06.17更新
04もう一つの日本『万葉集』
―《古雅なリズム感》《烈しい慕情の表現》《最古の写本は御物》―
古雅なリズム感
大和路(やまとじ)観光客のほとんどが、近鉄の桜井駅で降りてしまったあと、一つ先の朝倉駅はほとんど人影もない。初瀬川に沿って、旧街道を東へ向かう。
真夏の正午だというのに、黒ずんだ連子(れんじ)窓をぴたりと閉ざした民家の古い家並み。ところどころに成金臭い“豪邸”が新築されているが、目を見張るのはコンクリート塀(べい)の下部に用いられた巨大な茶色の庭石である。
黒崎村のはずれにくると、道の両側に開けた一面の稲畑になだらかな里山が迫ってくる。炎天下を歩くこと三十分、ようやく息切れがして、老農夫に「天(てん)の森はどこですか?」ときいてみた。
「ああ、それはよくお尋ねになる方があるだども、もう何もありませんでな。ほれ――」と、老農夫は左手の山の中腹を指差した。「あの竹林のあたりがそうだが、最近、庭石屋が買い占めてしもうてな。まあ、登って御覧なされ」
ゴロタ石の急な斜面を行くこと約百五十メートル。まず目についたのは、青瓦(がわら)の一見プレハブ風住宅と、その前方に中型のブルドーザー。そして、私の目的地である万葉伝承の地は、いまや例の茶色の庭石が掘り返されたばかりの白い地肌を見せているだけであった。慣れっことはいえ、現代日本の象徴的風景――。
汗が一度に噴出して、私はぺったりと石の一つに坐りこんでしまったのだが、そのときふと左手の稲畑に目をやった。小さな森を背景に、段々畑が初瀬の谷に続いている。近くに巻向(まきむく)山、遠く畝傍(うねび)山や香具(かぐ)山を見晴るかす大和の群山(むらやま)。
――私のなかに何かがこみあげてきた。
籠(こ)もよ み籠(こ)持(も)ち 堀串(ふくし)もよ み堀串(ぶくし) 持(も)ち この岳(をか)に 菜(な)摘(つ)ます児(こ) 家(いへ)聞(き)かな 告(の)らさね そらみつ 大和(やまと)の国は おしなべて われこそ座(ま)せ しきなべて われこそば告(の)らめ 家をも名をも
〔原文〕籠毛與 美籠母乳 布久思毛與 美夫君志持 此岳尓 菜採須兒 家吉閑名 告<紗>根 虚見津 山跡乃國者 押奈戸手 吾許曽居 師<吉>名倍手 吾己曽座 我<許>背齒 告目 家呼毛名雄母 《一・一》
よい籠(かご)に堀串(ふくし=土堀りの道具)を持って、この岳に菜を摘む乙女よ。おまえの菜は、家は。空(そら)見つ〔枕詞(ことば)〕大和の国は、このわたしが治め、住むところ。さあ、お言い、おまえの名は、家は……。
『万葉集』全二十巻、四千五百三十余首の巻頭を飾るこの歌は、「泊瀬(はつせの)朝倉宮(あさくらのみや)に天(あめ)の下(した)知らしめしし(統治せし)天皇(すめらみこと)」、すなわち、雄略天皇の歌とされる。もと民謡だったのかもしれず、伝承地もここだけではない。しかし、この段々畑と初瀬の山こそは、私が夢に描いた光景に確実に重なりあうものがあった。
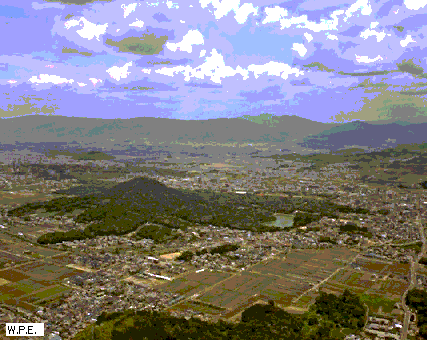
烈しい慕情の表現
黒崎の近く、白山比咩(ひめ)神社は雄略天皇の皇居があったと伝えられるところで、境内には保田与重郎(その2写真)による「万葉集発耀(はつよう)讃(さん)仰地」の碑がある。“参考地”にかけたのかもしれぬが、それはともかく、氏もまた天の森付近に立って、籠もよの地であるという実感を得たのではないだろうか。
実感といえば、天の香具山という山は意表外である。平原のなかにポッカリ浮かんだ、標高百五十メートル足らずの大地にすぎないので、この上に国見に立った舒明(じょめい)天皇が、「国原(くにはら)は煙(けぶり)立ち立つ 海原は鴎(かまめ)立ち立つ」と詠じたような雄大さは、容易に想像することができない。しかも、現在の香具山は頂上まで松が生い茂り、眺(ちょう)望も利かない。むしろ、遠望によって、その女性的な風姿を鑑賞するにしくはない。
春過ぎて夏来(きた)るらし白栲(しろたへ)の衣(ころも)乾(ほ)したり天の香具山
〔原文〕春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山 《一・二八》
女帝(持統天皇)らしい――いや、歌の世界では女性といわせてほしい――こまやかな、しかし悠然とした歌だ.。白栲は楮(こうぞ)の皮から作った布である。初夏の青葉を背景に、衣替えの白布が目に沁みる。亡き夫の天武天皇を偲(しの)んだ
やすみしし 我が大君の 夕されば 見したまふらし 明け来れば 問ひたまふらし 神岳の 山の黄葉を 今日もかも 問ひたまはまし 明日もかも 見したまはまし その山を 振り放け見つつ 夕されば あやに悲しみ 明け来れば うらさび暮らし 荒栲の 衣の袖は 干る時もなし
〔原文〕八隅知之 我大王之 暮去者 召賜良之 明来者 問賜良志 神岳乃 山之黄葉乎 今日毛鴨 問給麻思 明日毛鴨 召賜萬旨 其山乎 振放見乍 暮去者 綾哀 明来者 裏佐備晩 荒妙乃 衣之袖者 乾時文無 《二・一五九》
という慕情あふれる烈(はげ)しい表現とともに、古代の天皇のなかでも最も人間的な親しみをおぼえずにはいられない。
持統天皇の信任が厚く、天皇讃歌をはじめ多くの重厚な名作をのこしたのが柿本人麻呂だ。そのわりに、微臣として終わったが、のちの紀貫之の例に見るまでもなく、宮廷歌人の運命とはそんなものだ。
東(ひむかし)の野に炎(かぎろひ)の立つ見えてかへり見すれば月傾(かたぶ)きぬ
〔原文〕東 野炎 立所見而 反見為者 月西渡 《一・四八》
陶淵明の詩にヒントを得たというこの作品は、のちに蕪村の
菜の花や 月は東に 日は西に
へつながっていくが、人麻呂の世界はもう少しきびしい。炎(かぎろひ)は初冬の黎(れい)明を意味するといえば、のどかな情景ではありえないことがわかる。
朝倉から国道一六六号線に沿って約十キロ、大宇陀町の高原に阿紀神社がある。古代に安騎野(あきの)と称したこのあたりへ、狩りの供としてやってきた人麻呂は、亡き草壁皇子の思い出にひたりながら夜を明かした。きびしい高原の寒気。遠く伊那佐山から大師山にかけての連峰に、一瞬赤い曙光(しょこう)が射す。ふと西の空を見ると、青白い月は既に消えかかっていた。日月星辰(しん)の巨大な運行のなかに、小さな人事の有為転変が思い込められている。
だが、このドラマチックな万葉名所も、いま訪れる人は少ない。ほとんどは、かの高松塚から“村営”のサイクリングで檜隈(ひのくまの)大内(おおち)陵(天武・持統陵)を経て、蘇我馬子の墓といわれる石舞台へ向かう。その途中に橘(たちばな)寺があるが、県道は排気ガスが充満し、またもや村営の観光会館が目に飛び込んで、鄙びた田園情緒を損なっている。
橘の寺の長屋にわが率宿(ゐね)し童女(うなゐ)放髪(はなり)は髪あげつらむか
〔原文〕橘 寺之長屋尓 吾率宿之 童女波奈理波 髪上都良武可 《十六・三八二二》
右歌椎野連長年脉曰 夫寺家之屋者不有俗人寝處 亦稱若冠女曰放髪<丱>矣
然則<腹>句已云放髪<丱>者 尾句不可重云著冠之辞哉
読み人知らずの歌で、むかし寝た垂髪の少女はいま成人しただろうか、という意味である。
最古の写本は御物
『万葉集』はいうまでもなく、日本最古最大の歌集であり、その成立時期も五世紀から八世紀ごろまでの四百五十年間におよぶ。天皇、皇族のうた、民衆のうた、それも農民から防人(さきもり)、乞食(こじき)にいたるまで社会のあらゆる階層を含み、歌の形式も多様である。編者も一人ではありえないが、現在に近い形にまとめあげたのは大伴家持(やかもち)という説が有力だ。とにかく、当時はこれだけ幅広く人間と自然の営みを映した文学作品は、世界のどこにもない。
著名な歌人としては、やはり、人麻呂がスターだが、天智天皇、有間皇子、大津皇子、山部赤人、大伴旅人、高橋虫麻呂、笠金村(かさのかなむら)、大伴坂上郎女(さかのうえのいらつめ)、そして、末期には家持、田辺福麻呂、狭野茅上娘子(さののちがみのおとめ)、笠郎女(かさのいらつめ)、中臣宅守(なかとみのやかもり)などが、まず逸することのできぬ主要キャストである。
なにしろ、古いものだから、“万葉”の意味さえ定かではないが、常識的に「多くの歌」ということだろう。用字法は、万葉仮名(九百七十三字)で、平安時代にはすでに難解とされていた。これを天暦年間、源順(みなもとのしたごう)らがひらがなの訓をつけた。古点本という。その全貌(ぼう)は伝わらないが、巻四の一部が平安中期の写本として残っている。桂本(かつらほん)と称し、紫・藍(あい)・白・黄・茶・薄赤・草・朽葉などの各色を用いた継色紙に、金泥(でい)・銀泥で花鳥風月を描き、流麗な書体で原文と訓(よ)み下し体とが併記されている。百九首、十六張(ばり)四百九十三行、縦二十六・六㎝の巻子一軸だが、御物だから簡単に見るわけにもいかない。
このほか、平安末期の藍紙本、天治元年の天治本など多数の古写本があるが、いずれも断片である。現在の“総集版”は、鎌倉時代の中頃、僧仙覚が当時残っていた十数本を校合(きょうごう)したもので、これを新点本という。
明治、大正には正岡子規や伊藤左千夫、斎藤茂吉らが作歌の面で万葉調を実践した。だが、現在中年以上の世代には、第二次大戦中、大伴家持の、
海行かば水漬(みづ)く屍(かばね)、山行かば草むす屍
〔原文〕海行者 美都久屍 山行者 草牟須屍 《十八・四〇九四》
といった部分が悪用された記憶のほうが、はるかになまなましいであろう。
とにかく、『万葉集』の魅力は、日本というくにの創世紀の若々しい情熱と、素朴な人間のいぶきが、いのちあふれることば〔言霊(ことだま)〕のなかに躍動しているところにある。とくに巻頭の一首にあふれた、古雅でエキゾチックですらある日本語のリズム感が、二十代の私をこの書物の世界に誘い込んだのだった。それは“もう一つの日本”の発見ですらあったのだ。
現在、全巻見ることができるものとして、鎌倉時代の写しであるが西本願寺本『万葉集』(御茶ノ水図書館藏)がある。その他諸本については「万葉集諸本」を参照されたい。
[補遺]
よろづのことのは⇒「万葉集入門編」他。やまとうた⇒訓読『万葉集』
『万葉集』の古写本類 万葉集諸本輯影 尼崎本『万葉集』 廣瀬本『万葉集』
春の雪(大伴家持の世界) 源順と万葉集成立 枕詞一覧 万葉集巻5の中の「古今」
[付録]