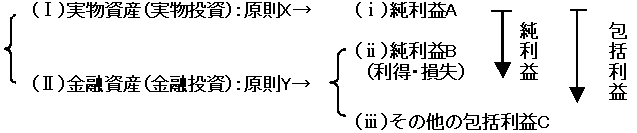
時価会計の基本問題
-金融経済の会計学-
大阪市立大学 石川純治
Ⅰ 何が問題か
Ⅱ 時価評価の論拠づけを巡って
Ⅲ 資本維持と資本・利益計算の体系問題
Ⅳ 擬制資本の会計問題
今日の会計制度においてもっとも議論されているテーマは有価証券に代表される金融商品の時価評価問題である(1)。それは金融の国際化・グローバル化を背景にした「制度」上の重要課題にとどまらず、会計「理論」としてきわめて重要な問題をはらんでいる。そこで、本稿では以下、何が理論上問題なのかを明らかにしたい。
Ⅰ 何が問題か
筆者はこれまで、今日の有価証券に代表される金融商品の時価論議において何が問題なのか、とりわけ会計理論としていくつかの問いかけを行ってきた。例えば、以下に示す問いは、いずれもきわめて基本的な問いであろうかと思われる。
Q
Q
1.2:有価証券の時価評価に伴う損益認識は「実現」概念の拡張(原価・実現主義の延長上)で説ける性格のものか?Q
1.3:そもそも「原価・実現主義」とは何であるか、今日の時価論議での金融商品はその捕捉対象となりうるものか?もしなりうるなら、そこでの「原価」とは何であるか(3)?Q
1.4:有価証券の時価論議と資本維持はどうかかわるか、かかわるならかつての価格変動会計での「資本維持」論争とどう異なるか?Q
1.5:今日の時価論議に「全面時価会計vs.全面原価会計」といった全面的対立の図式が描かれるのか、それとも時価会計と原価会計とは何らかのかたちで併存が可能か?もし可能なら、そこにどのような理論的根拠が示されるか?
Q
1.1は有価証券が商品という形態(金融商品)をとっていても、それが実物の製品・商品とはたして同じ「商品」といえるのかというきわめて基本的な問いかけであり、その答えいかんによっては評価問題の基本視点の分かれ目になりうる問いともいえる。その意味で、それはすべての問いのいわば出発点になっているということもできる。なお、拙稿 [1995]においては、Q1.1,1.2, 1.3に関していずれも否定的な考え方を示している。また、Q1.4,1.5に関しては最近の拙稿[1998]でひとつの答えを示している。
ところで、今日の時価論議を単に投資家のための情報「開示」の問題としてだけではなく(4)、利益「計算」の問題として論じるとなると、そこに会計理論にとって重要な問いが投げかけられる。拙稿 [1997a]でも論じたように、以下の問いはその例である。
Q
Q
2.2:経済的実体や潜在的リスク開示の背後にある思考は、そもそも損益計算とかかわりうるものなのか(6)?Q
2.3:「資産・負債アプローチ」と「収益・費用アプローチ」とは単なる利益計算の異なるアプローチにすぎないものか?とりわけ、今日の時価論議においてはどうか、2つのアプローチに何らかの「ギャップ」がありはしないか?
Q
2.1は今日の時価開示の議論が、はたして「適正な期間計算」といったこれまでの利益計算の枠組みのなかでどのようにおさまりうるのか、またQ2.2はそのことをより基本的な会計思考のレベルで問うたものである(7) 。今日の時価論議には経済的実体開示とか潜在的リスク開示といった(投資家にとって有用な)ディスクロージャー論が全面にでており、利益計算がその背後あるいは後回しになっている。いわば「枠組み論」・「仕組み論」ぬきの「役立ち論」が先行しており、そこにどのような会計思考が出てきているのか、とりわけ資本・利益計算の枠組み論(貸借対照表論とか損益計算書論)での、かつての「静態論」 (static theory)とか「動態論」(dynamic theory) といった思考比較がなじまない議論となっているように思える。Q2.3は今日の時価論議の背景に「資産・負債アプローチ」がありながら、他方で例えば収益の認識基準である「実現」概念を拡張する議論があるように(その意味で収益・費用アプローチ)、いったい2つのアプローチは単に利益アプローチの仕方の相違にすぎないのか、それとも2つのアプローチの間に何らかの「ギャップ」があるのかをあらためて問うたものである。
これらの問いは、これまでの会計枠組みの延長、あるいはバージョンアップといったレベルではなく、その構造そのものを基本的に問うものであるといえる(詳しくは拙稿
[1997a] を参照)。そして、今日の時価論議に伴う損益計算の問題は、結局のところ具体的には「包括利益」 (comprehensive income)という利益概念に焦点が当てられ、その性格を問うことになる。以下の問いはその例である。
Q
Q
3.2:なぜ、一方で包括主義をとりながら、他方で時価評価に伴うある種の利得・損失を純利益計算に入れないという“矛盾”があるのか(8)?Q
3.3:「包括利益計算書」は包括主義の延長線上に位置するものであるか?そうでなければ、どのような新たな展開が行われているか?Q
3.4:利益の「リサイクル」という考え方は、未実現評価損益(その他の包括利益項目)の性格をどうみていることになるか?リサイクルしない方法はどうか?Q
3.5:その他の包括利益は純利益計算からみて純利益の経過的・繰延的性格にすぎないものなのか? もしそうであるなら、純利益と区別されるのは単に実現までの期間にすぎない、そういった利益がそもそも1つの利益概念として認められるのか?
これらの問いは、拙稿
[1997c]および拙稿[1997b]で論じているので参照されたい。要は、 Q3.5 ともかかわって、包括利益なる利益概念は「何をどう包括しているのか」という問いに集約されるといえるだろう。
筆者はこれまで、以上の基本問題を公表された論文も含めて、以下にかかげる論点として論じてきた。
Ⅰ)異種の資本と資産分類問題
Ⅱ)原価主義会計の捕捉対象問題
Ⅲ)擬制資本の会計問題
Ⅳ)包括利益の3つの基本問題
Ⅴ)時価評価の論拠づけ問題
Ⅵ)リサイクル問題と2つの利益問題
Ⅶ)公正価値会計と資本維持問題
Ⅷ)資本・利益計算体系の再構成問題
本稿では、公表された拙稿での議論との重複をできるだけ避け、特に論点のⅤ
(以下、第2節)、Ⅷ(以下、第3節 ) およびⅢ (以下、第4節)を中心に論じてみたい。
Ⅱ 時価評価の論拠づけを巡って
1 2つの資産区分と利益の認識・測定原則
今日の時価論議を特徴づけているのは何かといえば、その対象が実物経済活動(実物投資)ではなく金融経済活動(金融投資)であり、そこからでてくる資産(金融資産)の評価問題であるということである。このことは、例えば国際会計基準委員会(IASC)の最近の討議資料(
1997 年3月)でも明確な見解が出てきている。すなわち「生産的な収益産出活動」に対する会計と、「変換・実現の過程によらない」金融資産に対する会計との区分がそれである(9) 。
そこで、この実物資産(非金融資産)と金融資産の区別に即して、そこからでてくる利益の認識・測定原則の全体像を描けば理論的には図1のように示される。包括利益が2つの資産区分とともに、
(i)純利益A,(ii)純利益B、 (iii) その他の包括利益Cの3層構造として示されていることに注意されたい(10)。
図1 実物資産・金融資産と利益の認識・測定原則
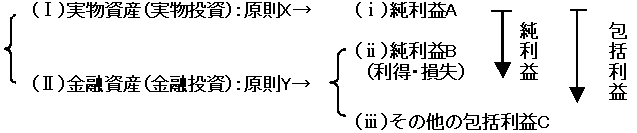
図1の原則XはIASC討議資料での用語を借りれば「生産的な収益産出活動」での利益認識・測定原則であり、それは現行のいわゆる「原価・実現」原則、「収益・費用対応」原則を基礎にする期間損益(純利益)計算にほかならない。問題は、原則Yであり、とりわけ伝統的な原則Xとの関連である。 2 実現概念の何らかの再考
これまで原則Yに関してもっとも多くなされてきた議論は、実現概念の何らかの再考による論拠づけである。それも、詳細に吟味すればさまざまな論拠づけがあり、それを筆者なりにまとめてみれば以下のようになる(11) 。
①実現概念の拡大
FASB
②実現概念の再解釈
測定の「信頼性」、利益の「確実性」→実現主義そのもの適用(=広義の実現主義)
③「実現」と「認識」との分離
包括利益の定義「企業の持分について認識される全ての変動」→未実現利得損失が「認識」の対象(包括利益にとって「実現」は要件とならない)
④「発生主義会計という枠組み」
(原価・時価併存体系)での実現主義生産基準、販売基準、回収基準もいずれも同じく実現主義の具現形態、資本の時間的貸与
⑤実物投資と金融投資の区別:投資の性格と評価基準
金融資産の時価の変動=キャッシュフローの実現
⑥購入銘柄と購入のタイミングを選択する努力の業績評価
有価証券の保有利得=事後の成果
⑦実現主義の制度的・発展史的相対化:売却主義の実現と購入主義の実現
購入で実現(統制経済→買うことは同時に売れたこと)
①および②は伝統的な実現概念そのものを拡大ないし再解釈するもので、実現概念の再考のなかでもとりわけよく用いられる論拠づけである。これに対し、③はそうした実現概念の延長上での捉え方ではなく、「実現」と「認識」とを分離することで実現の要件などそれに付随する論議を不要のものにしている。④は発生主義会計という全体としての会計システム(原価・時価併存体系)から、その一貫として収益認識基準を捉え、とりわけアキュムレーション法の原理による論拠づけがなされている(12) 。⑤は実物投資と区分された金融投資にあっては、時価の変動そのものが実現利益であり、確定した投資成果の指標となるという論拠づけがなされている。⑥は販売面ではなく購入面から、すなわち銘柄選択と購入タイミングの業績評価という観点から論拠づけるところに特徴があるといえる。最後に、⑦は幾分古い文献であり、また金融商品の時価評価問題とは直接かかわるものではないが、実現主義をその経済基礎の発展史的考察から相対的に捉えるところ、とりわけそこから「購入主義の実現」という議論がなされているところに特徴があり、ここに取り上げておいた。以上、この他にも取り上げるべき説もあるかと思われるが、とりあえずはその概観は得られたであろうと思われる。
ところで、こうした
(Ⅰ)実現原則の何らかの再考による論拠づけは、それが時価評価を導く唯一の論拠というわけではない。とりわけ、それが収益の認識原則である実現概念の再考であること、すなわち(評価)損益の認識から資産の時価評価がでてくること(一般的に表現すれば、フロー評価→ストック評価)に注意したい。これに対し、例えば有価証券=貨幣性資産、有価証券=現金同等物、有価証券自体=自由選択性資金、などと捉える考え方は、広い意味で( Ⅱ)貨幣性資産として規定する論拠づけ (回収可能額=時価→評価損益の認識) ということができるであろう。そこでは、実現概念を論じる必要はなく、また先の「評価損益の認識→時価評価」とは逆の規定、すなわち「時価評価→評価損益の認識」(ストック評価→フロー評価)という規定になることに注意したい。さらには、(Ⅲ) 収支概念の拡大による論拠づけ、あるいは後述する(Ⅳ)新たな資本維持概念による論拠づけ、といった別の観点からの論拠づけの可能性が考えられる。以上、まとめれば次のようになる。
(Ⅰ)実現概念の何らかの再考による論拠づけ
(Ⅱ)貨幣性資産として規定する論拠づけ
(Ⅲ)収支概念の拡大による論拠づけ
(Ⅳ)新たな資本維持概念による論拠づけ
いずれにしても、ここでは実現概念の何らかのかたちによる再考だけが唯一の論拠づけではないことを強調しておきたい。とりわけ、実現概念の拡大・再解釈アプローチによる全体としての会計枠組みの再構成問題は、それが伝統的な「実現」概念の拡大・再解釈であるかぎり、論理的にいって伝統的な損益計算の枠組みの拡大・延長上での再構成(現行の会計枠組みの“バージョンアップ”)ということになるだろう。
3
「その他の包括利益」と認識・測定原則問題図1の原則Yを論じるにあたって、さらにもうひとつ問題がある。すなわち同じく金融資産からの利益が、一方で
(ii) 純利益Bを構成し、他方でそれと区別される(iii)その他の包括利益Cを構成する、その「区別の論理」は何かという問題である。とりわけ、それが(開示優先思考からくるところの)政策・制度論としてではなく、理論すなわち損益計算論の問題としてはどうなのか、ということである。この区別の論理を検討するにあたって、評価差額の2つの処理方法(「リサイクルする方法」
vs. 「リサイクルしない方法」)がひとつの参考になる。すなわち、リサイクルする方法では実現される以前の(その他の包括利益項目としての)評価損益が、実現時にその他の包括利益から実現時の損益計算書(純利益計算書)に移される。となると、売却以前の(未実現)評価損益は、とりもなおさず純利益の経過的・繰延的性格をもつ損益にすぎないということになる。したがって、ここに純利益と区別されるのは単に実現までの期間にすぎない、そういった利益すなわち“繰延純利益”なる利益がそもそも認められるのか、という問題が指摘されることになる(13) 。そして、そもそもそうした性格をもつ(リサイクルされる前の)評価損益そのものは、いかなる理屈で純利益でない利益なのか、このことが問われなければならない。このことはたとえリサイクルしない方法をとったとしても同じである。理論的にいえば、図1の(純利益と区別されている)
(iii)その他の包括利益を認識・測定する何らかの原則が明示されてはじめて区別の論理が明らかになるといえる(14) 。経営者の保有目的や意図といった区別の基準が、はたして損益論としての区別の論理といえるかどうか。もし損益の認識・測定論としての区別の論理が示されないなら、それは認識・測定原則いかんというよりも、「はじめに時価評価ありき」の実体開示要求との妥協的産物(「開示」優先と「計算」との妥協)ということになってしまうであろう。先の純利益の繰延的・経過的処理としてのその他の包括利益はそうした“妥協の現れ”とみることもできうる。そうであるなら、むしろ妥協する前に、実体開示要求を損益論とは切り離して別個対応することのほうが、よっぽど理論としてすっきりするといえるだろう。
いずれにしても、拙稿
[1997c]で論じたように、その他の包括利益が“第2の”利益なのかどうか、したがって2つの利益が認められるのかどうかという問題は、個々の「その他の包括利益」項目の検討をとおして、とりわけそれらがすべて上記の意味での“繰延純利益”項目なのかどうかの検討をとおして、包括利益は「何をどう包括しているのか」という理論的課題として検討されなければならないといえる(図2参照)。図2 2つの利益問題
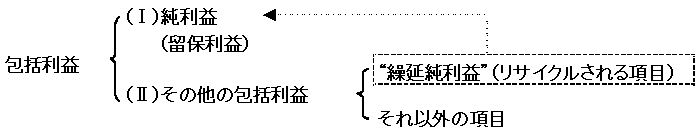
Ⅲ 資本維持と資本・利益計算の体系問題
利益計算にとって資本維持はその確定基準となるものであり、金融商品の時価評価からでてくる利益計算もその例外ではないであろう。そうであれば、先の(Ⅳ)新たな資本維持概念による論拠づけは、(資本・利益計算としての)会計理論にとってきわめて重要であるといえる。この点については拙稿[1997c],[1998]で詳しく論じているので、ここでは特に資本維持概念を基礎にする全体としての資本・利益計算の体系問題についてだけふれておきたい。
今日の時価評価に伴う利益計算を資本・利益計算としての会計体系のなかにどう位置づけるかは、個々の会計問題とともに、あるいはそれ以上に重要な問題である。本来的には、まずその「全体」が明らかにされ、その位置づけのなかで個々の会計問題が説かれなければならないであろう。しかし、学界もふくめて今日の議論の多くは、「全体論」ぬきの「個別論」が先行しているようにみえる。
さて、全体を問うとき、それが1つの資本・利益計算としての体系であるなら、資本が利益確定の基準となる以上、維持されるべき資本概念のなんらかの統合なくして1つの会計体系は考えられないであろう。例えば、拙稿
[1998]で論じたように、IASCはその討議資料(1997年3月) において金融商品に適用可能な新たな資本維持概念を提示しながらも(15)、それが貨幣資本維持であることをもって(現行の名目資本維持とともに)1つの貨幣資本維持体系としての会計枠組みを想定している。またFASBも、「包括利益は貨幣資本からの利益(return on financial capital)である」(SFAC No.6, par.72)に示されているように、包括利益のなかに仮に純利益と区別されるある種別個の利益があったとしても、その全体は貨幣資本維持体系ということになる。いずれにしても、そこでの資本・利益計算は貨幣資本維持という統合概念によって1つの会計体系ないし枠組みが想定されているといえる。問題はそこでの貨幣資本のなかみであるが、IASCもFASBもその概念フレームワークにおいて(実体資本維持が現在原価での評価を必要とするのに対し)貨幣資本維持は特定の測定基礎と結びつかないことに言及している(IASC
[1989]para.106, SFAC No.5 para.47) 。要するに、名目貨幣単位であれ恒常購買力単位であれ、あるいは公正価値単位であれ、期首の純財産の貨幣額(これが維持されるべき貨幣資本)を期末のそれが超過するものがreturn on financial capital(貨幣資本利益)ということであろう。となると、仮に(資産全体ではなく)資産の種類に応じて、企業が維持したいと望む「貨幣資本の種類 (type of financial capital)」(IASC[1989]para.106)が異なったとしても、全体としては貨幣資本維持としての1つの利益計算体系ということが可能となる。まさに、IASC討議資料が金融資産(ないし負債)に公正価値評価を、非金融資産に現行の原価評価を適用することが「非整合的ではない」(Ch.1 para.6.10)といわしめる理屈はここにあるように思える。しかし、「異種の貨幣資本」から構成される全体として資本・利益計算を、それらがすべて貨幣資本であるということをもって、1つの貨幣資本維持体系として十把一絡げに論じてしまうことに問題はないのであろうか
(16)。とりわけ、そこから出てくる「異種の利益」の側からみれば、拙稿[1998]で論じたように、名目貨幣単位と公正価値単位からでてくるそれぞれの利益の性格はあまりにも違いすぎるように思える(17) 。したがって、全体としての資本・利益計算の体系を問う問題は、依然として重要な検討課題であるということができる(18)。
Ⅳ 擬制資本の会計問題
1 現実資本の会計と擬制資本の会計
先に、今日の時価論議を特徴づけているのは、その対象が実物経済活動(実物投資)ではなく金融経済活動(金融投資)であり、そこからでてくる資産(金融資産)の評価問題であるということを指摘した。そのことをその背後にある経済的資本の側からみれば、今日の時価評価問題は、それが「現実資本」ではなく「貸付・擬制資本」にかかわっているというところにその特徴がある。すなわち、今日の時価問題は、その経済的背景をふまえて図式的に示せば、
(i)証券資本主義の今日的拡大化・高度化現象:米国を中心にした投資家資本主義(インベスター・キャピタリズム)の時代 → (ii)財務的リスクの管理と情報開示の重要性 →(iii)開示および会計問題(資産・負債評価問題)として現象:資産・負債の評価問題(B/S問題)+それに伴う利益の認識・測定問題(P/L問題)
とでもなろうが、より理論的レベルあるいは概念的レベルでいえば、今日の時価会計の対象は「現実資本」
(real capital)ではなく「貸付・擬制資本」(credit/fictitious capital) であり、その資本運動がその基礎にあるということである。このことは、例えば同じ時価論議であっても、今日の時価論議がかつての「価格変動会計」とはその本質を異にしているという重要な見方の理論的基礎を提供するといえる(図3参照)(19)。ところで、擬制資本を対象とする会計問題は今回がはじめてというわけではない。わが国で
1950年代になされたいわゆる「株式プレミアム論争」では、それが「資本会計の問題」(貸方側の問題、発行側の問題)として議論されたわけで、それが「資産会計の問題」(借方側の問題、投資側の問題)として登場してきたのが今回の擬制資本の会計問題といえる(20)。現実資本の会計とともに示してみれば、図3のようになる。図3 擬制資本の会計問題
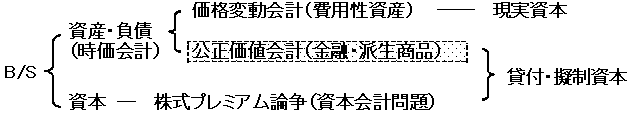
株式プレミアム論争ではその経済学的本質規定から会計問題を解くという方法がとられたように、今日の会計問題をまずは経済学とりわけ金融経済学上のキー概念にその手がかりを求め、それとの対応をとおして会計学上の概念を相対的に位置づける、こういった試みがひとつの方法として考えられる。「現実資本の会計」
vs.「貸付・擬制資本の会計」という捉え方はその集約されたものにほかならず、とりわけ強調されるべきは、その区別が今日の会計問題を解くにあたってひとつの重要な見方になりうるということである。2 金融経済学上のキー概念と会計概念の相対化
会計学の対象が会計実践であり、会計実践の基礎に経済実践がある以上、会計(学も実践も)それ自体がひとり独立に存在するというわけではない。そうであれば、その基礎にある経済実践、とりわけその発展形態との対応で会計概念を相対化することは、理論化のためのひとつの重要な作業といえるだろう。
そこで、ここでは特に①資本、②利潤、③信用、④価格形成について示しておこう。図4の矢印の右側で示されているすべてが、今日の時価論議の基礎にあるキー概念であることに注意されたい。
図4 金融経済学上のキー概念
①資本:商業資本、生産資本→ 貸付資本、擬制資本、そのさらなる擬制化
②利潤:商業利潤、産業利潤→ 利子、利回り、投機利潤
③信用:商業信用(流通信用)→ 資本信用
④価格形成:費用価格 → 株式価格(価値なき商品)
例えば、拙稿[1995]でも論じたように、③信用制度の歴史的発展形態(流通信用と資本信用との区別)からみた会計概念の検討はその一例であり、その観点からすれば先の第Ⅱ節で述べた有価証券を貨幣性資産として同一資産範疇に規定することの問題点が指摘される
(21)。また、④経済的基礎を異にする価格形成の本質的区別(費用価格と擬制資本価格) の視点からすれば、「原価・実現」の延長・拡大アプローチの問題点は明らかであろう。さらに、個々の会計概念については、例えば①経済学的資本概念の区別からは、拙稿[1995]でも論じたように、会計上の資産概念とりわけ伝統的な資産分類(貨幣性資産と費用性資産)の妥当性の吟味、②利潤の区別からは、「質的にいえば利子のいっそう無概念的な姿」であり、「一切の契約的要素の拘束から解放された純粋に市場的な現象」(川合[1954]pp.50-51 、傍点は筆者)であるところの「利回り」に象徴されるように、伝統的な実現利益概念(名目資本維持利益)とは異なる利益概念の可能性(従って伝統的利益との混在可能性)が検討されよう。いずれにしても、今日の会計問題を「擬制資本の会計問題」と捉えたとき、かつての株式プレミアム論争や、さらには擬制資本としての性格をもつ土地、のれんも含めて、擬制資本の会計問題の全貌が示され、そのなかで今日の問題を位置づけるというさらなる視点も重要であろう。そのとき、(制度・政策も含めて)今日の会計問題を困難にしているもののひとつが現実資本ではなく擬制資本であり、とりわけその成立・発展過程に応じて会計問題として現象してくるということも明らかになるであろう
(22)。
*本稿は『会計理論学会年報No.12』(1998年10月発刊予定)の拙稿「時価会計の基本問題」に基づいて作成したものである。
(
1998年5月)
引用文献
IASC, Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements, 1989.
――――, Accounting for Financial Assets and Financial Liabilities, Discussion Paper,1997.
FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No.5 1984, No.6 1985.
――――, Reporting Comprehensive Income, Exposure Draft, 1996
川合一郎『資本と信用-金融経済論序説-』有斐閣、
1954年井尻雄士「アメリカ会計の変遷と展望」『会計』第
153巻第1号、1998年1月拙稿
[1995] :「原価・時価論争と資本循環シェーマ」『経営研究』第46巻第2号、1995年8月――
[1997a]:「時価会計と損益計算」『経営研究』第48巻第1号、1997年5月――
[1997b]:「時価会計と“第2の”損益計算書構想」『JICPAジャーナル』No.507、1997年10月――
[1997c]:「利益の『リサイクル』とは何か」『経営研究』第48巻第3号、1997年11月――
[1998]:「金融商品に適用されうる資本維持概念について」『産業経理』第57巻第4号、1998年1月
Fundamental Issues of Fair Value Accounting
Junji Ishikawa
Osaka City University
The author has first shown some fundamental issues of fair value accounting as follows: I) the different concepts of capital and the assets classification problem, II) the problem of the object of the historical cost accounting , III) the accounting problem of fictitious capital, IV) the three fundamental problems of comprehensive income, V) the theorization problem of fair value valuation, VI) the “recycle” problem and the two types of income problem, VII) fair value accounting and the capital maintenance problem, and VIII) the reconstruction problem of the system of the capital/income calculation. In this paper especially, problems V (section2), VIII (section3), and III (section 4) are discussed avoiding a repetition of the discussions in my previously published papers.
In section 2, we examine the most popular approach to theorizing the fair value valuation of financial instruments , i.e., (i) a reconsideration of the traditional “realization” concept, and show that this approach is not the only way of the theorization. In addition to the most commonly used approach, this paper shows that the following approaches could also be considered: (ii) a prescription of financial instruments as financial assets, (iii) an expansion of the concept of cash revenue/payment (Einnachme- Ausgabe), and especially (iv) an introduction of a new capital maintenance concept for financial instruments.
In section 3, we examine the system of the capital/income calculation which is composed of different types of financial capital such as nominal financial capital (for non-financial assets) and current market rate of return capital (for financial assets). From the view point of the different types of income arising from the different types of financial capital maintenance, the author poses the question of whether the system should be considered as one undifferentiated, integrated, singular system, i.e., a financial (or money) capital maintenance system, or as a compound system which is composed of sub-systems, i.e., the different types of capital/income calculation systems.
In section 4, though several approaches could be considered in order to discuss current accounting problems as a social science based on an accounting methodology in accordance with the main theme of the 12th annual research meeting , this paper shows a possibility of theorizing based on the distinction between accounting for real capital and accounting for credit/ fictitious capital, and emphasize that the distinction is a quite important view point for resolving current accounting problems.