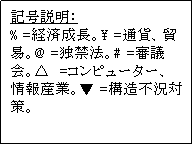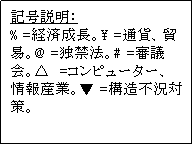|
|
|
�����{�o�ώj���N�\ |
|
2008/4/22 |
|
|
|
|
|
|
���@����@�� |
|
|
���@�Y�Ɛ���֘A�@�� |
|
|
|
|
|
|
|
| @ |
1945�| |
������́A�_�n���v�A�J�����v |
|
1945.8 |
���H�Ȃ̕����A�Ŗ��i�R���ȑO����) |
|
|
1946 |
�V�c�̐l�Ԑ錾 |
|
|
|
GHQ�ɂ��f�ՊǗ� |
|
| @ |
1946-51 |
������А����ψ��� |
|
|
1945 |
�f�Ւ��i�O�ǁj |
|
| @ |
1947 |
�Ɛ�֎~�@�A��������ψ��� |
|
1946 |
�X�ΐ��Y����-49 |
|
| @ |
1947 |
�ߓx�o�ϗ͏W���r���@ |
|
|
|
�F�o�������{����65�o�ϊ�撡 |
|
| \ |
1948 |
�����O�E���|�[�g |
|
|
|
|
| \ |
1948.12 |
�o�ψ���X�����F�P��בփ��[�g |
|
|
|
| \ |
1949.4 |
$1=\360���{�y�Œ����ꐧ�ցz |
|
1949.5 |
�ʏ��Y�Əȁ����H�ȁ{�f�Ւ� |
|
|
1949.4 |
�h�b�W�E���C�� |
|
|
|
�@��,�G��,�@�B,���w,�S�|;�ΒY,�d�� |
|
|
1950 |
�V���E�v���������{ |
\ |
1949.12 |
�O���בy�ъO���f�ՊǗ��@ |
|
|
|
|
\ |
1950.5 |
�O���Ɋւ���@�����O���Z�p���� |
|
|
1950.6 |
���N�푈-53�A�����i�C |
|
|
|
���Y�ƍ��������� |
|
|
1951 |
�T���t�����V�X�R���a��� |
# |
1949.12 |
�Y�ƍ������R�c��������������̐� |
|
| \ |
1952 |
IMF�����A14���� |
|
# |
1951.2 |
�Y���R���\�F�킪���Y�Ƃ̍��������� |
|
| \ |
1953 |
IMF����4430������ގؓ� |
|
1951.5 |
���{�J����s���ݔ������̒ᗘ�Z�� |
|
| @ |
1953 |
�Ƌ֖@�ɘa�G���ٔF�� |
|
|
1951.4 |
�S�|��ꎟ�������v�恨1956�� |
|
| \ |
1953 |
GATT�̏������� |
|
|
1952 |
�Ȗa�ыƂɊ������Z |
|
| \ |
1955 |
GATT�̐��������� |
|
|
1952 |
������ƈ���@�F�D���� |
|
|
|
|
|
1952.3 |
��ƍ��������i�@ |
|
| @ |
1954 |
�O�H������ |
|
|
|
�@�F���ʏ��p�A���H�`�p���� |
|
| @ |
1958 |
�O�䕨�Y�Č� |
|
|
|
���Y�ƈ琬�i�U���j���� |
|
|
|
|
|
1953 |
�����@�ۍH�ƈ琬�܃��N�v�� |
|
|
|
�����x�o�ϐ����� |
|
|
1955 |
�Ζ����w�H�ƈ琬�� |
|
| % |
1955-57 |
���ʌi�C�A�_���i�C�@31���� |
|
1956 |
�S�|��������v�� |
|
| \ |
1956 |
IMF����1.25����َؓ� |
|
|
1956.5 |
�@�B�H�ƐU���Վ��[�u�@ |
|
|
1956 |
�V���D�����E���A�p�������� |
|
|
��61�`�A�O��66�` |
|
| % |
1957-58 |
�Ȃג�s�� |
|
�� |
1957.6 |
�d�q�H�ƐU���Վ��[�u�@ |
|
| % |
1958-61 |
��ˌi�C�@42���� |
|
|
|
�F�g�����W�X�^�[�A�R���s���[�^�[ |
|
|
|
|
|
|
�w���B�ɂ�����č����{�̐i�o�x |
|
| \ |
1960 |
�f�ՁE�ב֎��R���v���j |
|
|
1960 |
IBM�����̌��J |
|
| % |
1960.12 |
���������{���v��/GNP�d�� |
|
# |
1960 |
�Y���R���Ұ��ݕ���\ |
|
| % |
1961-62 |
�i�C��� |
|
# |
1961.4 |
�Y�ƍ\��������� |
|
| % |
1963-64 |
�I�����s�b�N�i�C |
|
\ |
1961.6 |
���ʍ|�����i�ƍ|�ނ̗A�����R�� |
|
|
1963 |
���₪��������� |
|
�� |
1961 |
���{�d�q�v�Z�@��JECC�ݗ����J��Z�� |
|
| \ |
1964 |
IMF�W�����ցAOECD�ɉ��� |
|
|
1962 |
�Ζ��Ɩ@�F�Ζ�������Ђ̓��� |
|
|
|
���O�݊������P�p |
|
|
1963 |
����Y�ƐU���Վ��[�u�@���p�� |
|
| % |
1965 |
�l�\�N�s���i�،��s���j |
|
|
|
�@�F�����w,����|,������ |
|
|
1965 |
�R��،����ɓ�����ʗZ�� |
|
# |
1964 |
�Y�ƍ\���R�c��� |
|
|
1965 |
���ݍ����s |
|
|
1965 |
�Ȗa�s���J���e�� |
|
| % |
1965-70 |
�����Ȃ��i�C�@57���� |
|
\ |
1965.10 |
������p�Ԃ̗A�����R�� |
|
|
1968 |
GNP���E��2�ʂ� |
|
|
1966 |
���Y�����Ԃ��v�����X�����Ԃ����� |
|
| \ |
1967 |
��P�����{���R�� |
|
|
1966 |
÷���ݽ����Ђɏ����t���������� |
|
| \ |
1969 |
��Q�����{���R�� |
|
�� |
1968 |
MIS�̊J������ї��p�Ɋւ���� |
|
| \ |
1970 |
��R�����{���R�� |
|
�� |
1969 |
�Y�\�R�E���Y�ƕ���\:MIS |
|
|
|
|
@ |
1970 |
�V���S���� |
|
| % |
1971 |
�s�� |
|
|
|
�@���������S�{�x�m���S��1950���� |
|
| \ |
1971.8 |
�j�N�\���E�V���b�N |
|
|
|
|
|
1971 |
�X�~�\�j�A������@$1=\308 |
# |
1971.5 |
�Y�\�R���ԓ��\�u70�N��̒ʏ��Y�Ɛ���v |
|
| \ |
1971.8 |
��S�����{���R�� |
|
|
|
�F�m���W��Y�� |
|
| \ |
1972.5 |
�O�ݏW�����x�p�~ |
|
�� |
1971 |
����d�q�H�Ƌy�ѓ���@�B�H�ƐU���Վ��[�u�@ |
|
|
|
1972 |
�c���ʎY���̓��{�����_ |
�� |
1971 |
�Y�\�R�E���Y�ƕ���ԓ��\ |
|
| \ |
1973 |
��Q���f�Վ��R�� |
|
�� |
1972 |
�d�q�v�Z�@���J�����i��⏕�� |
|
| \ |
1973 |
��T�����{���R�� |
|
|
|
|
|
1973.2 |
�~���ϓ����ꐧ�ֈڍs $1=\264 |
|
|
|
|
1973.10 |
���V���b�N�i�������j |
|
|
|
|
|
1974.2 |
�Ζ���݃J���e������ |
|
�� |
1974 |
�Y�\�R�E���Y�ƕ���ԓ��\ |
|
| % |
1974 |
�}�C�i�X�����@��㏉ |
|
|
|
|
|
1975 |
�Ԏ��������s�@��������@���� |
|
|
|
| % |
1975-80 |
���萬�� |
|
�� |
1976 |
���G���G�X�A�C�Z�p�����g�� |
|
| @ |
1977 |
�Ƌ֖@�����F�ے������x�Ȃ� |
�� |
1978 |
����@�B���Y�ƐU���Վ��[�u�@ |
|
| \ |
1979 |
�V�O�ז@�F�ΊO��������R�� |
�� |
1978 |
����s���Y�ƈ���Վ��[�u�@ |
|
|
1979 |
����V���b�N |
|
|
|
�@�F�d�F,�A���~,���@,���D |
|
|
1980 |
�Ζ��J���e���������ٔ��� |
|
|
|
|
|
1980 |
�z���_���I�n�C�I�H��\ |
�� |
1981 |
�Y�\�R�E���Y�ƕ���\�u80�N��̏�y�я��Y�Ƃ̂�������тɂ����ɑ���{��v |
|
|
|
1981.3 |
�������Վ��s�������� -83 |
|
�� |
1983 |
����Y�ƍ\�����P�Վ��[�u�@ |
|
|
1981.5 |
���������A�o�����K�� |
|
|
|
�F�d�F,�A���~,���@,���w�엿,��,���� |
|
|
1982 |
IBM�Y�ƃX�p�C�����F�����A�O�H |
|
|
|
|
|
1985 |
NTT��JT������ |
|
|
|
|
|
1985.9 |
�v���U���ӁF�~���h���� |
|
|
|
|
| % |
1985 |
�~���s�� |
|
|
|
|
| % |
1986-91 |
�����i�C�i51����)�A�o�u���o�� |
|
|
|
|
1986 |
�O�����|�[�g�����\ |
|
|
|
|
|
1986 |
�������������� |
|
|
|
|
| % |
1986 |
���l������GDP��������� -97 |
|
|
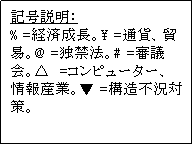
|
|
|
1987 |
���S���c���AJR���� |
|
|
|
|
|
1988.12 |
����Ŗ@�ċ��s�̌� |
|
|
|
|
|
1988 |
���������Y�����E�s����50%�� |
|
|
|
|
1989.4 |
����Ŏ��{��3�� |
|
|
|
|
| \ |
1989.5 |
���₪�����������������3.25%�� |
|
|
|
| \ |
1990.4 |
�呠�Ȃ��s���Y�Z�����ʋK���@�o�u������� |
|
|
1991.10 |
������U�ŏ،�4�Ђ��c�ƒ�~���� |
|
|
|
|
1995.1 |
��_��W�H��k�� |
|
|
|
|
|
1995.3 |
�I�E���^�����̒n���S�T�������� |
|
|
|
| \ |
1995.4 |
1�h��79�~75�K�@�ō��l |
|
|
|
|
|
1996.2 |
�nj���������Q�G�C�Y�Ő��{�ӔC��F�߂� |
|
|
1997.4 |
����ł�5���Ɉ����グ |
|
|
|
|
| @ |
1997.6 |
�Ƌ֖@�����F������������Ȃ� |
|
|
|
|
1997 |
��������������� |
|
|
|
|
|
|
�쑺�،��A�����،��A��a�،��A |
|
|
|
|
��ꊩ��A���≮�A�O�H������ |
|
|
|
|
1997.11 |
�O�m�،�������X���@�K�p���\�� |
|
|
|
1997.11 |
�k�C����B��s���c�ƌ������n |
|
|
|
|
1997.11 |
�R��،�������p�� |
|
|
|
|
|
1998 |
�呠�ȁE���⊲�������d�őߕ� |
|
|
|
|
1998.10 |
���{�����M�p��s���ꎞ���L�� |
|
|
|
|
1998.12 |
���{���M�p��s���ꎞ���L�� |
|
|
|
| \ |
1999.2 |
���₪�[�������ւ̗U���� |
|
|
|
|
|
1999.9 |
JCO�ŗՊE���� |
|
|
|
|
| % |
1999 |
���Ɨ����č������� |
|
|
|
|
|
2000.4 |
���ی����x�J�n |
|
|
|
|
|
00.7 |
�u�������v���j�] |
|
|
|
|
| \ |
00.8 |
���₪�[��������������� |
|
|
|
|
| \ |
01.3 |
���₪�ʓI�ɘa����� |
|
|
|
|
|
01 |
���S���������T������ |
|
|
|
|
|
02.11 |
�����f�t���� |
|
|
|
|
|
02.11 |
�|����b�����Z�Đ��v���O�����̎��{�菇��� |
|
|
|
|
|
|
|
|
| \ |
06.03 |
�������ʓI�ɘa�����������B�[���������ێ� |
|
|
06.11 |
�i�C�g��������Œ��A�u�����Ȃ���z�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04 |
����22���Z�@���̃T�u�v���C�����[���֘A������24���~�� |
|
|
|
�@07�N7���`08�N3�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|