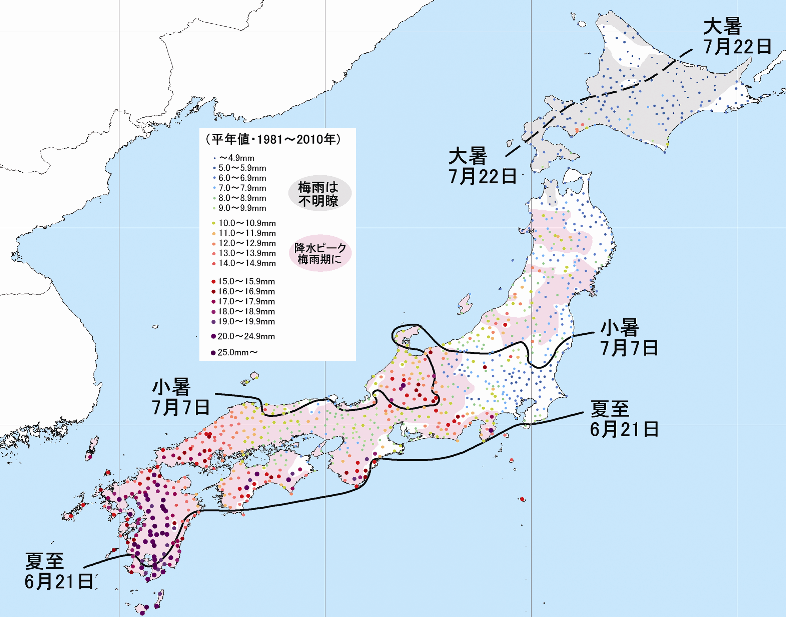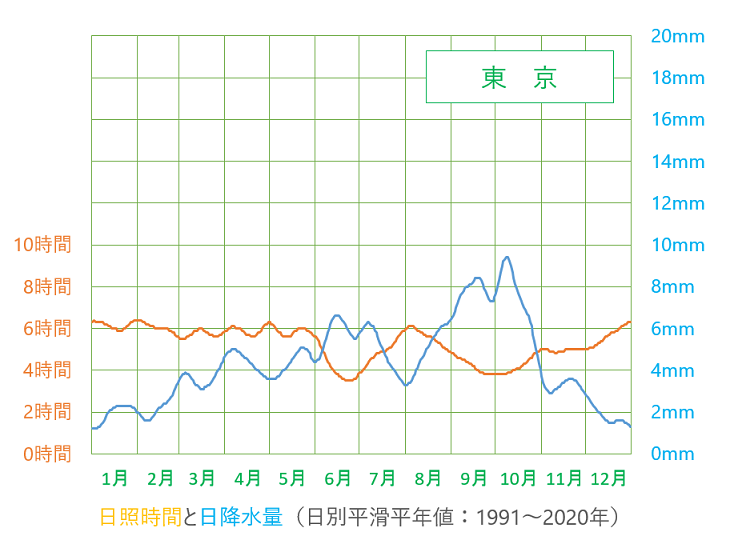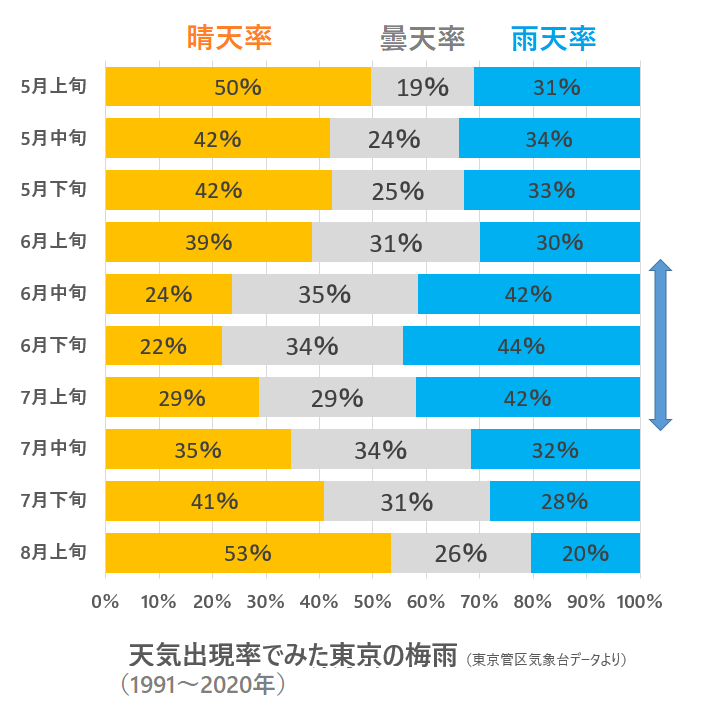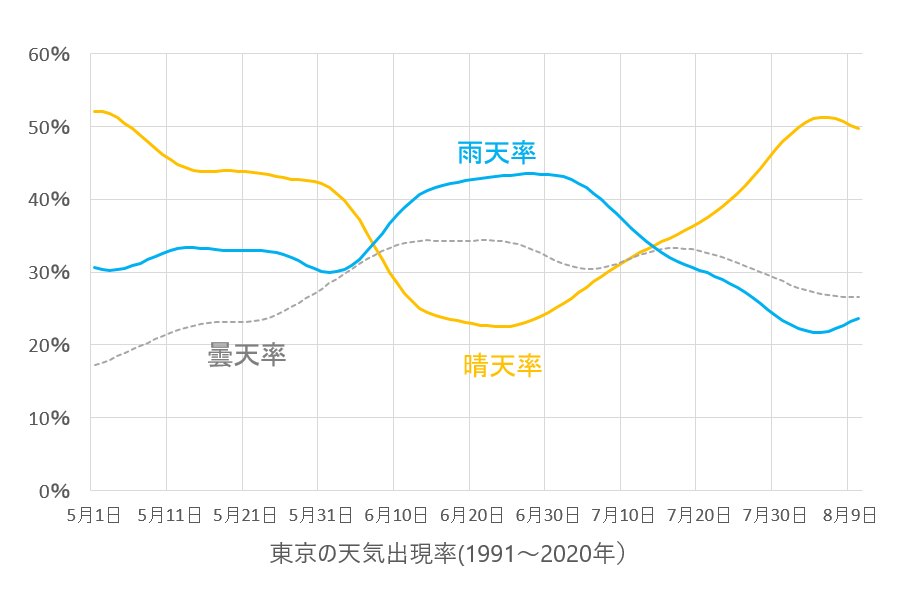前のページ
梅雨前線のしくみ
梅雨前線を模式図的に示しました。
一般に梅雨前線は、その北側300キロ以内が雨のエリアとなり、
そのさらに北側400キロがくもり空のエリアとなります。
なお、梅雨前線の西側部分では、前線の南側でも雨が降り、大雨になることがあります。 |
日本付近の梅雨前線の構造は西と東で違います。
前線というのは、性質の違う空気の境目にできます。
梅雨前線は東西に寝ている前線ですから、
前線の北側と南側で空気の性質が違うことになります。 |
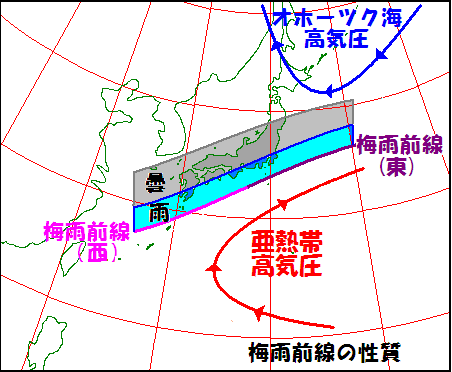 |
西の梅雨前線は、
「高温乾燥空気」と「高温湿潤空気」の境目にあります。
南北の空気の性質の違いは、湿り気の違いにあります。
前線の南側では湿った蒸し暑い空気が
流れ込みやすい状況です。
この湿った空気は別名「湿舌」と呼ばれます。
かつては豪雨の原因と説明されていましたが、
最新の研究では、暖湿流の流入とともに、
活発な積乱雲から放出される熱の影響で、
温度や湿度が高くなっているエリアと説明されます。
東の梅雨前線は、
「低温湿潤空気」と「高温湿潤空気」の境目にあります。
南北の空気の性質の違いは、空気の温度の違いにあります。
前線の北側では湿った冷たい空気(北東気流)が
流れ込みやすい状況です。
この湿った空気は別名「やませ」と呼ばれ、
梅雨明けが遅れると冷害の原因となります。 |
梅雨の最盛期の雨量
図をクリックすると大きな画像が開きます。*旧平年値(1981〜2010年)で作図したものです。
梅雨の雨の降り方は西と東で違います。
過去30年の平均データ(平年値・日雨量)でもその違いははっきり現れます。
関東と九州では、梅雨の最盛期の雨量が大きく違います。
関東の梅雨は「シトシト」、九州の梅雨は「ザーザー」、印象はまったく違うと思います。
日別降水量(平年値)の比較(東京と熊本)
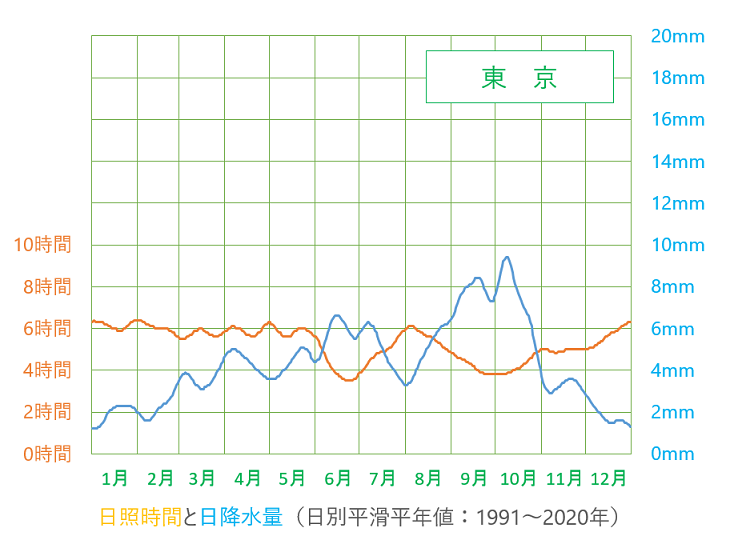
|
マウスをグラフに重ねると熊本のグラフにかわります。
熊本の梅雨の最盛期の雨量は、東京の3倍以上あります。
東京では、梅雨よりも秋雨の時期の雨量の方が多くなります |
梅雨期間の天気出現率
天気出現率を帯グラフでみたものです。統計期間は1991年〜2020年です。
日平均雲量8.5未満を「晴天」、日降水量1.0mm以上を「雨天」としています。
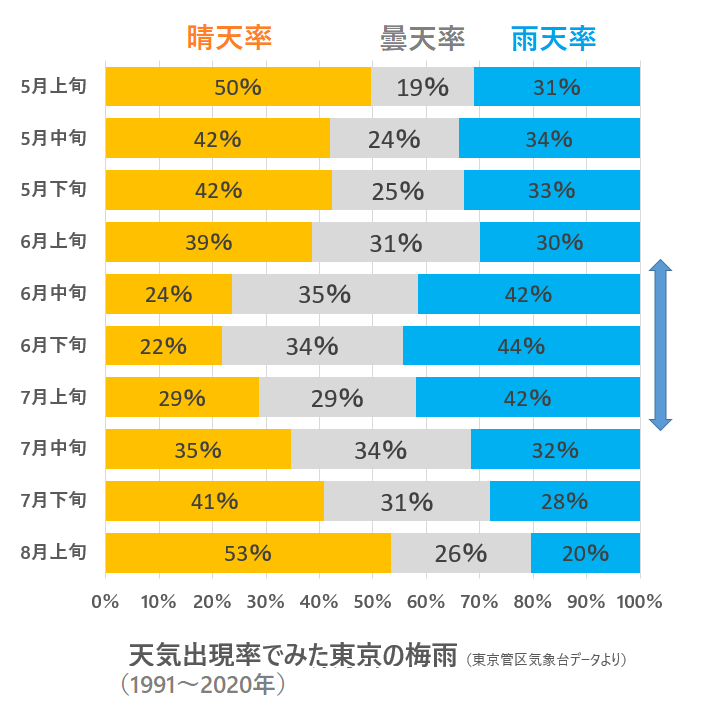 |
6月中旬から7月上旬にかけては、雨天率が晴天率を上回ります。
晴天率<雨天率 の期間を梅雨と定義するなら、
6月中旬から7月上旬が気候学的な「東京の梅雨」と定義できそうです。
さて、多摩川河川敷でバーベキュー大会を開催しようと、参加者に都合を聞いたところ、
6月下旬と7月下旬ならば、全員が参加できることがわかりました。
さて、幹事であるあなたは、どちらの時期にバーベキュー大会を実施しますか? |
天気出現率からみる東京の梅雨
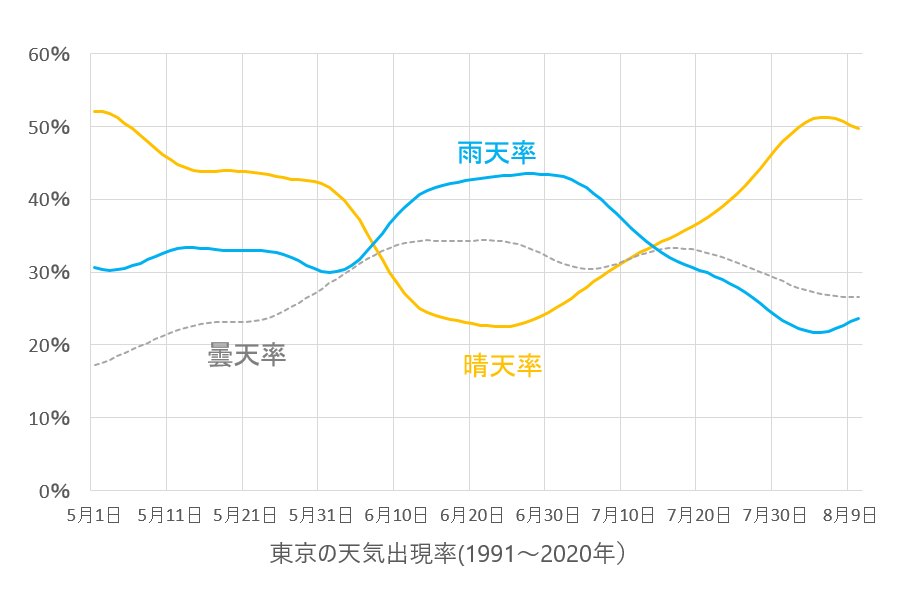 |
東京の天気出現率のグラフです。データは日別ですが、9項移動平均を3回やって滑らかにしています。
雨天率が晴天率を上回る頃を「梅雨入り」とするなら6月7日頃となります。
(ちなみに気象庁による関東甲信の梅雨入りは、平年では6月7日頃です。)
晴天率が雨天率を上回る頃を「梅雨明け」とするなら7月13日〜14日頃となります。
(ちなみに気象庁による関東甲信の梅雨明けは、平年では7月19日頃です。)
|
次のページ