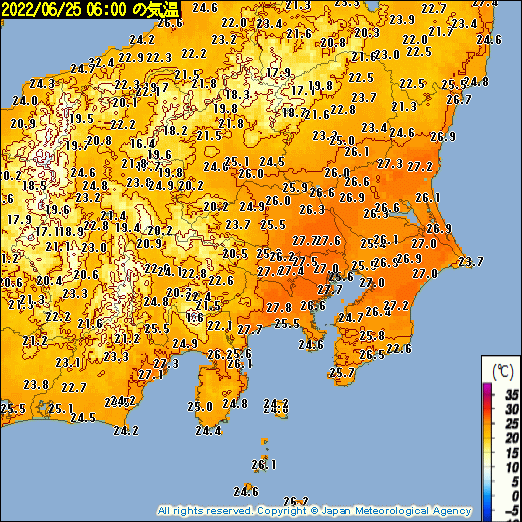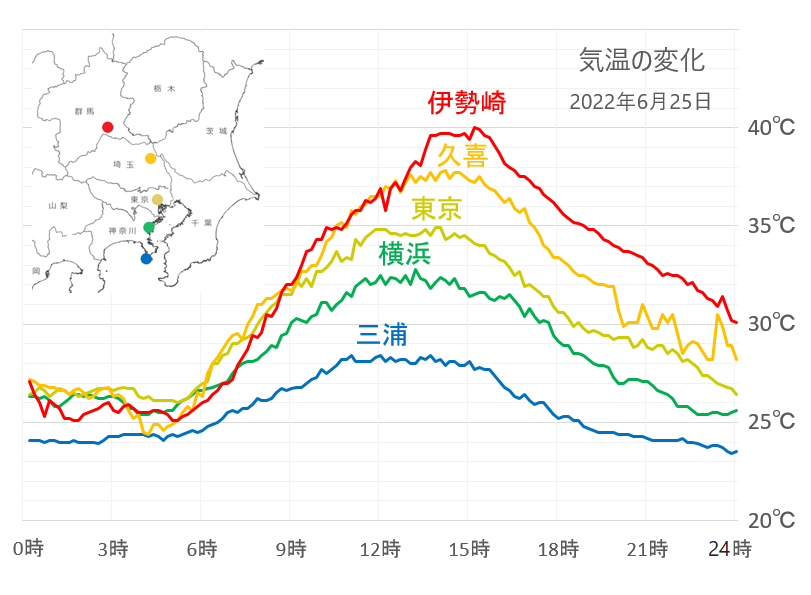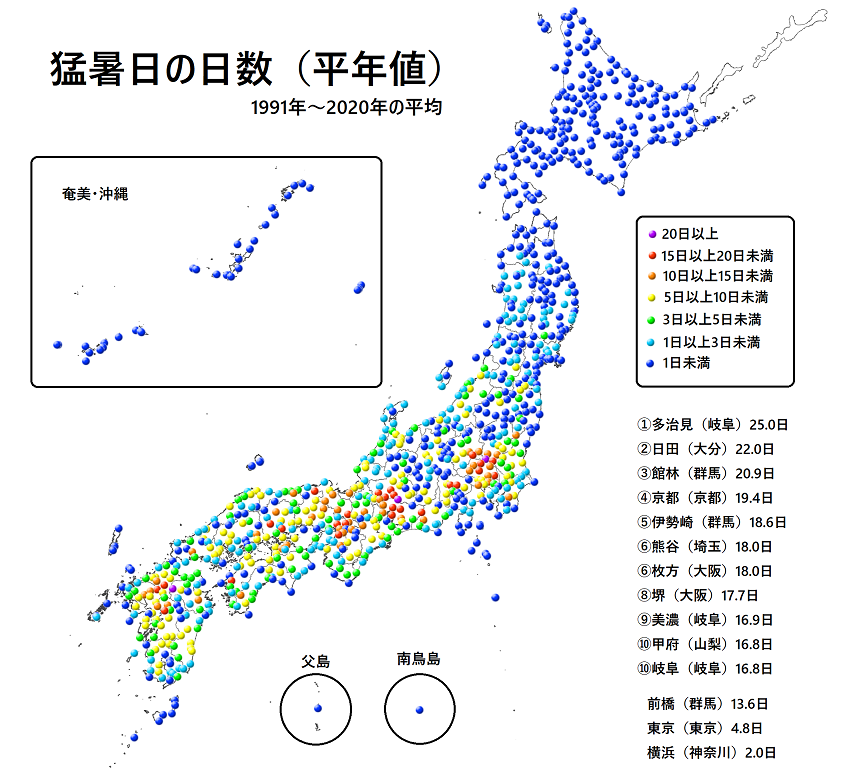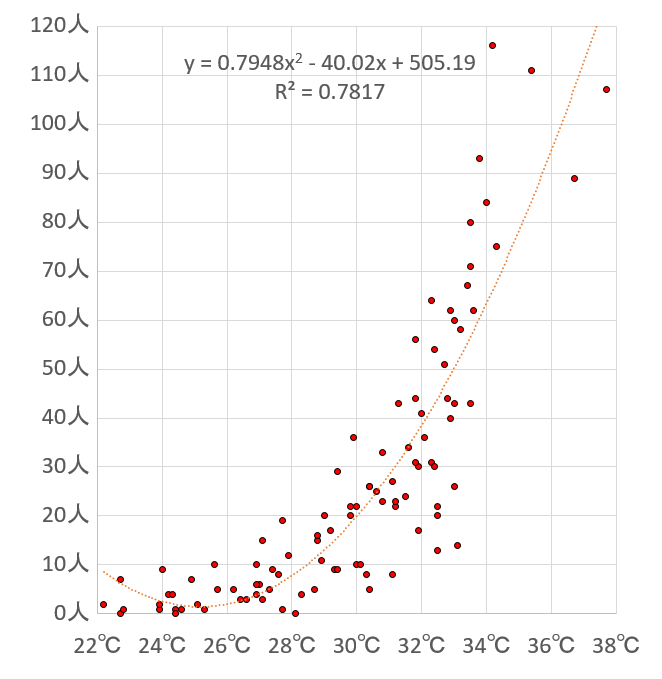猛暑とヒートアイランド
2022年6月25日は、関東内陸を中心に記録的な暑さとなりました。
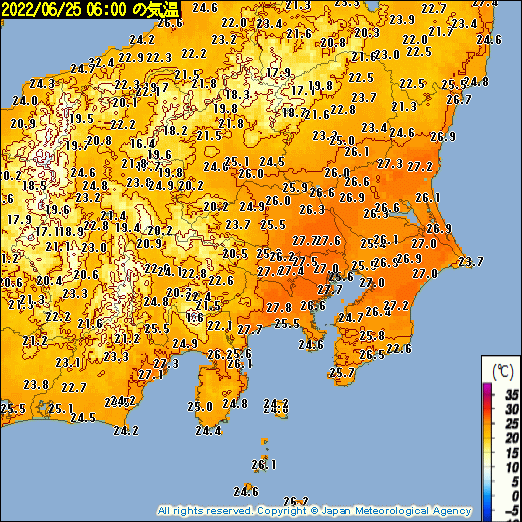 |
気象庁が公開している「推計気象分布(気温)です」
アメダスの観測された値をもとに
標高を勘案しつつ、空間内挿したものです。
6月25日は、関東平野の内陸部を中心に
最高気温35℃以上の猛暑日となり、
群馬県伊勢崎市では、
最高気温が40.2℃まであがりました。
気象庁の観測点で6月に40℃以上となったのは、
はじめてのことです。
これまで最も早い40℃以上は、1998年7月4日に
群馬県上里見で観測された40.3℃でした。
伊勢崎は、群馬県内では高温となりやすいところで、
2020年8月11日にも40.5℃まで上がっています。
2022年6月25日の最高気温(KML)
40℃以上の記録一覧
(2022年6月25日現在) |
【沿岸と内陸気温上昇量の違い】
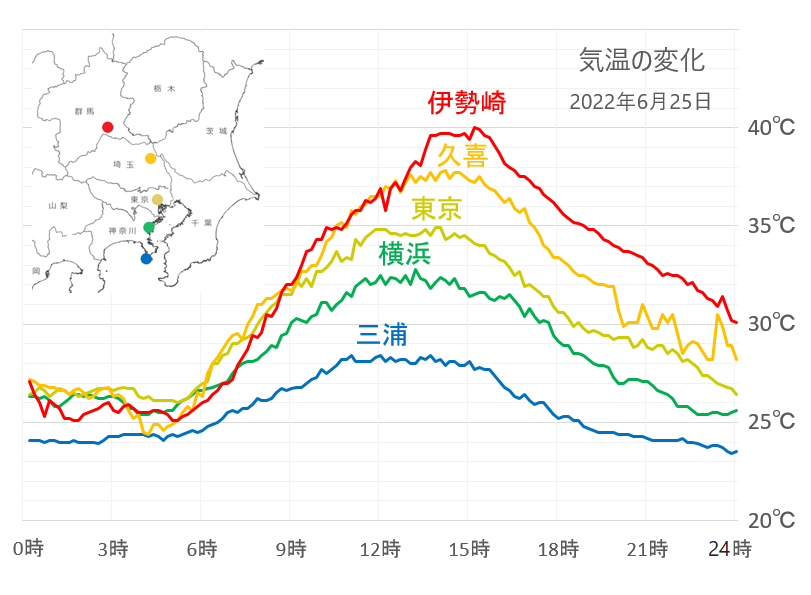 |
2022年6月25日には、東京都心の最高気温も35.4℃まであがり、観測史上最も早い時期の「猛暑日」となりました。
関東でも場所により、温度の上昇量に違いがみられました。それはどうしてでしょう?
|
猛暑日の日数
最高気温が35℃以上になった日のことを「猛暑日」といいます。
まずは、平年(1991年〜2020年の平均)の猛暑日の日数の分布図を見てみましょう。図をクリックすると大きな図が表示されます。
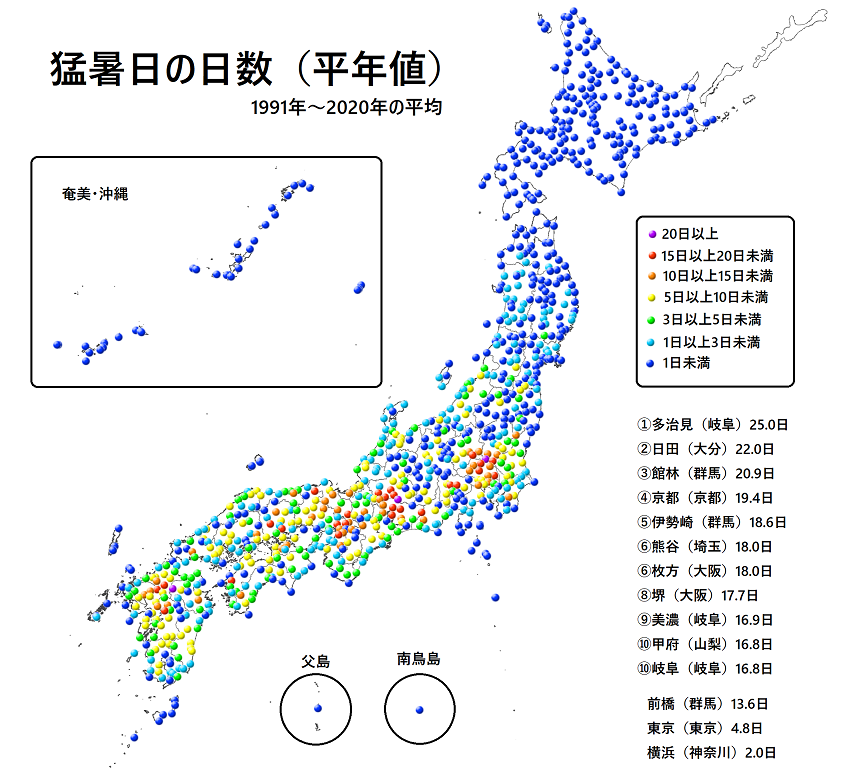 |
分布に偏りがありますか?
猛暑日が多いのはどこか?まずは大局的に眺めて法則性を見いだしてください。
「大原則」が見つかったら、その例外を探してみてください。
暑くなりやすい場所の特性を見いだすことが出来ますか? |
高温と熱中症
下のグラフは、総務庁消防庁がまとめたもので、東京都内の熱中症患者搬送者数です。
 |
複数の因子を1枚のグラフに重ねてみると、関係が見いだされることがあります。
熱中症搬送者が100人を超えるような日の最高気温は何℃位でしょうか?
熱中症搬送者が、毎日増加しているような期間は、最高気温はどう変化していますか?
急に涼しくなるような期間は、熱中症搬送者数がどう変化していますか?
いくつかの「法則」らしきものを読み取ってみましょう。 |
最高気温と搬送者数との関係をみたものです。
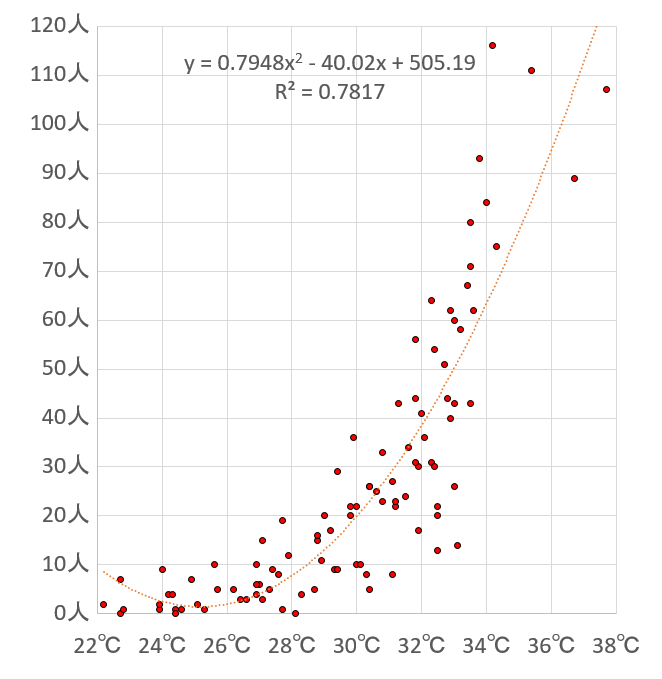 |
最高気温と搬送者数の関係をみたものです。
熱中症は、
最高気温28℃位から
患者が出始め、
33℃以上になると、
患者は急増すると言われます。
もちろん地域によって
暑さへの耐性は違うでしょう。
例えば、北海道の人は、
東京の人より低い気温で、
熱中症になるのかも知れません。
2016年夏の結果をみると
最高気温27℃以下なら、
搬送者数は10人以下と
なっています。
近似線を読み取ると、
30℃で20人、
32℃で40人、
34℃で60人強
36℃で90人強
となっています。
真夏日の状況下では、
2℃高くなると、
患者が20〜30人増える
ことになります。
相関が高いことから、
予想最高気温から
搬送者数を予想できます。
例えば32℃の予想だったら、
40人位の搬送者が想定され、
多ければ56人、
少なくても17人位の搬送者が
想定されると判断できます。
|
気温の変化と電力需要
気温が高くなると、冷房の使用頻度が高くなり、電力需要が増加します。
記録的な猛暑となった2010年夏のグラフを下に示します。
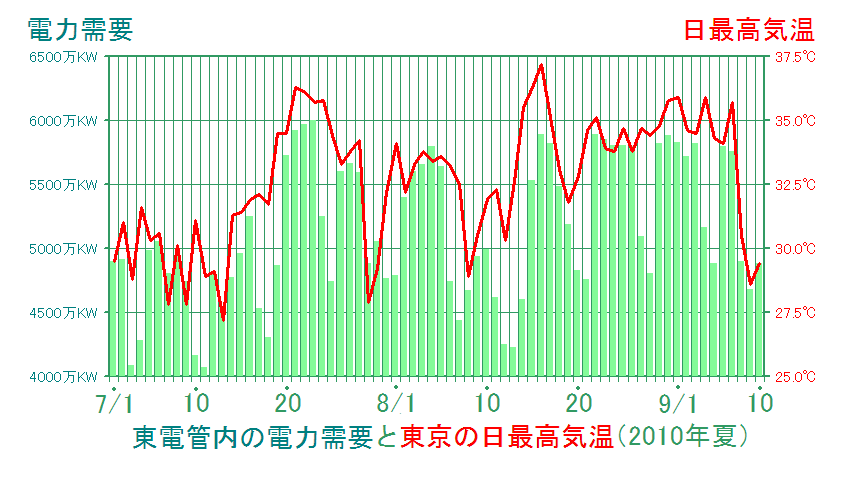 |
マウスを持っていくと棒グラフの色が変わります。オレンジは、土日祝日とお盆休みです。
最高気温が30℃を超えると、どのくらいの電力需要が見込まれますか?
最高気温が35℃を超えると、どのくらいの電力需要が見込まれますか?
ちなみに2011年夏のピーク時最大供給力は5500万KWが限界と言われていますが.... |
下の散布図は東京の最高気温と電力需要との関係をみたものです。
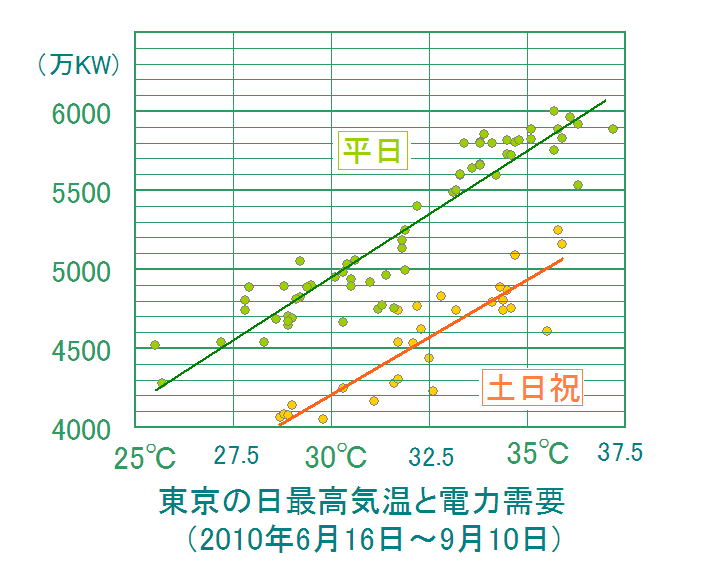 |
平日について相関係数はR=0.93、土日祝(お盆休み含む)について相関係数はR=0.79となります。
平日の回帰式は、電力需要=159.71×日最高気温+160.69
土日祝の回帰式は、電力需要=144.29×日最高気温-123.1
これを予測式として使えば、気温がわかれば、電力需要が予想できることになります。 |
次のページ