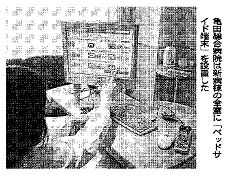2006年06月26日『日本経済新聞』朝刊第2部
第2部・日経ネット10周年特集 ― 安全・便利を実感、変わる医療現場。
患者と情報共有
遠隔診断も普及
ICTが医療の現場を変えつつある。インターネットを活用して入院生活の快適性を高め、患者が自分の病気について詳しく知るなど従来にないサービスが誕生。患者の放射線画像データなどを専門医とやりとりする遠隔画像診断も広がり始めた。
外房の海を臨む亀田総合病院(千葉県鴨川市)。昨年4月、全個室の新病棟「Kタワー」(364室)が完成した。様々な機能を持った「ベッドサイド端末」と呼ぶタッチパネル式の端末を全室に設置した。
食事の選択や検査の説明、買い物代行など端末から利用できるサービスは10項目に上る。患者はいつでも自由に使うことができ、テレビを見たりネットを利用したりもできる。
例えば自分が受ける検査の内容を画像や動画を交えて詳しく知ることができ、治療に対する理解が深まる。有料の買い物代行サービスは職員が院内外へ買い物へ出かけ必要なものを買ってきてくれる。
亀田総合病院は電子カルテを他の医療機関に先んじて1995年に導入するなどICTの活用に積極的だ。「毎年、総収入の3%をICT投資に充てている」(亀田信介院長)ほどで、2005年度は十億円程度を投資した。
患者が自分の病気について医師と情報共有できるシステムもある。医療情報システム開発のメディヴァ(東京・世田谷、大石佳能子社長)が開発した「オープンカルテ」だ。このシステムを使えば、患者は自分のカルテをネットで見られる。
オープンカルテは電子カルテを導入した施設がカルテ情報をデータセンターに送り、患者は同センターにアクセスして自分のカルテを見られる仕組み。自分の症例や検査内容、治療経過などを確認でき、処方薬の効能や副作用を調べる辞書機能もある。
経済産業省の委託事業で02年に開発。このほどほぼすべての市販の電子カルテに対応できるようシステムを改良した。複数の診療所が採用し、累計で約3千人が利用登録している。
ネットは遠隔画像診断の普及も後押しする。コンピューター断層撮影装置(CT)や陽電子放射断層撮影装置(PET)など画像診断機器が増える一方、放射線科の専門医は不足気味。ネットを使えば常勤の専門医が不在の病院でも、患者は質の高い医療を受けることができる。
セコム子会社で遠隔診断ビジネス最大手のセコム医療システム(東京・渋谷)は放射線科医を70人超抱える。このほど光ファイバーで画像の送受信ができるようになった。契約医療機関は約270施設と着実に増えている。