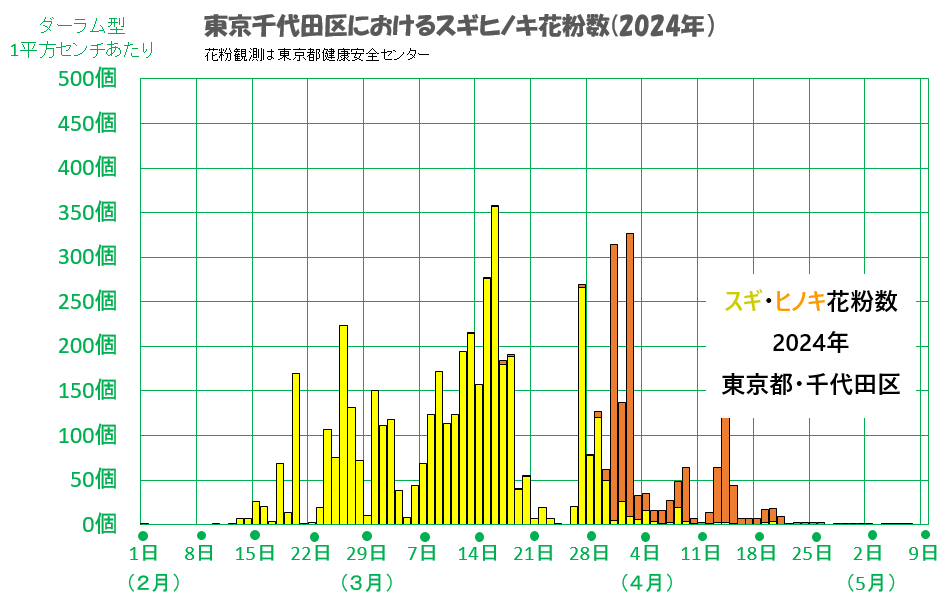
黄色がスギ花粉、橙色がヒノキ花粉。7日毎に目盛線を入れました。
顕微鏡観測の花粉数の場合、
1日あたり50個で、くしゃみ鼻水などの症状が強くなり、100個以上になると「とても辛い」日となります。
東京では、例年、バレンタインデーの頃からスギ花粉が飛び始めます。
そしてホワイトデーの頃にピークとなります。
また、ヒノキ花粉はホワイトデーの頃に飛び始めて、お花見の頃にピークとなります。
2024年は、2月13日よりスギ花粉が連続的に飛び始めました(1個/cm2以上、2日以上連続)。
例年どおりの飛び始めでした。
2月20日には100個/cm2を超え、花粉症患者にとって非常につらいシーズンに突入しました。
スギ花粉が最も多く飛んだのは3月16日(357個)でした。
ヒノキ花粉は、3月16日から連続的に飛び始めました。
例年通りの飛び始めでした。
3月31日頃からスギ花粉を上回るようになりました(スギ5個、ヒノキ309個)。
もっとも多くのヒノキ花粉が飛んだのは、4月2日で、ヒノキ花粉だけで318個も飛散しました。
東京のシーズン総花粉数は、スギが70%、ヒノキが30%のことが多いのですが、
2024年はスギ76%、ヒノキ24%でした。
2018年〜2022年のグラフはこちら
年ごとの傾向をつかんでみましょう。